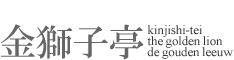Lucien Alphonse Gros (1845-1913) In Wikimedia Commons マウリッツ公のロッテルダム凱旋(歴史画)
八十年戦争のハイライトともいえる「ニーウポールトの戦い」には、「まるでポエジーのような」ともいわれるエピソードが随所に散りばめられています。メイン記事には載せきれない(むしろ筋を追うのには邪魔?)のでここに人物別にまとめました。逆にあらすじを知らないと何のことかよくわからないかもしれませんので、まずは下記をどうぞ。
メイン記事はこちら → ニーウポールトの戦い
ちなみに、ニーウポールトのエピソードには、上に挙げたロマン主義絵画のような想像の産物もたくさんあります。ここには基本的には17世紀当時の、しかもできるだけその場に居た当事者が書いたものをメインにし、その他19世紀の記述も交えて集めました。もっとも、リアルタイム時点で既に、事実を美化したり創作したりした逸話が存在していたなんて指摘もあります。格好いいっぽい台詞は太字にしていますが、念のため、それなりに意訳はしているものの、管理人による妄想エピソードは一切ないことを予めお断りしておきます。
ナッサウ伯マウリッツ
Paulus van Hillegaert (1633-1635) In Wikimedia Commons ニーウポールトの勝利ののち贈られた白馬に跨るマウリッツ公
ナッサウ伯マウリッツ
オランダ軍総司令官。主役を張る一人のため、もっともイメージの捏造が多いです。とくに戦いに臨んで、
「前にはスペイン軍、後ろには海である。戦死するか、溺死するか、それともスペインに打ち勝ち凱旋するか――兵士諸君と、運命を共にしよう」 *1
…と演説して全軍を鼓舞したというエピソードは、孫引きされるうちにこの位置に持ってこられただけで、戦闘前の台詞ではありません。そもそも全体に聞こえる演説のできるような地形でもありません。実際の戦闘前は、個別の連隊(同じ母国語を喋る集団)内で、独自に鬨の声を上げていただけのようです。たとえば「新乞食」と呼ばれるワロン連隊は、つい数ヶ月前にスペイン軍からオランダ軍に寝返ったばかりの連隊でした。いつ裏切るかわからない、と最もその忠誠心を疑われていたこの連隊は、仮の連隊長であるナッサウ伯フレデリク=ヘンドリク(未成年のため名ばかり連隊長で実際の指揮はしません)の名を叫んで、異様に見えるほどハイテンションでデモンストレーションをしていたようです。
本人のことばとして伝わっているのは最終局面でのものです。歩兵が総崩れになって退却を始めたとき、マウリッツは予備の騎兵隊に向かって「まだ希望は失われたわけじゃない、お前たちが居る」と呼びかけ、続いて突撃を命じました。
1.「私への愛を示すなら、我が軍の勝利のため、諸君らが誉れ高き男であると証明してみせよ」 *2
2.「勇気ある諸君が絶望を振り払うことを、成すすべなく溺死か虐殺の憂き目に遭うよりも、進んで戦死を選ぶことを願う」 *3
1.はその場にいた騎兵将校が仏語で記したもの、2.は同じくその場にいた政治家が蘭語で記したものです。いずれも数日内に書かれたものですが、立場によって若干受け取りかたが違うのも面白いですね。1.の高飛車感は、いかにも自分も命令する立場の人間による「勝って来い」の体育会系ノリですし、2.は文民らしく「死んで来い」をやや詩的に言っています。この2.のほうが戦闘「前」の演説として伝わった元ネタかと思われます。
同じ場面を描いた日本語の本(19世紀アメリカの文献からの抄訳)には、「軍人らしく祖国のために死のう」的な台詞も紹介されていましたが、これはややニュアンスが違っています。どちらにしてもオランダ軍は多国籍軍ですから、「祖国」に訴えかけること自体不自然で、このような記述がされたのもロマン主義時代のナショナリズムの影響でしょう。
同時代には「アルマダの戦い」の際のエリザベス女王の「ティルベリー演説」があり、真偽取り混ぜてこのような司令官演説が伝わるのも、同様のヒロイズムが求められたためかもしれません。
ヴィアー卿フランシス
Charles Rochussen (1854) In Wikimedia Commons おそらく足を怪我して下馬しようとしているのがフランシス(歴史画)
ヴィアー卿フランシス
前衛のイングランド軍の将軍フランシスは、軍制改革前からマウリッツのオランダ軍を支援してきた古参の中の古参の将軍です。マウリッツからの信頼は絶大で、常時必ず相談されていました。ところが決戦前夜、スペイン軍接近の報を受けて深夜に緊急将校会議が行われたとき、フランシスだけが会議に現れませんでした。
「いつものことだが、マウリッツ公は決断がトロいんだ。(中略)そしてその夜、私は寝ていたところを3度も起こされた。」 *4
即断即決の印象のあるマウリッツですが、実は周りに何度も相談しては相当な長時間ぐずぐず悩むのです。その代わり一度決断をくだすと、その後は何があっても絶対にその決定を覆すことはしません。フランシスは長い付き合いからそのどちらもよく心得ていました。結論だけ知れればそれで事足りるので、フランシスは勝手に一人で寝に戻ってしまったようです。それでもフランシスは使者が来るたびに起こされたというので、マウリッツが悩んでいた時間は随分な長時間だったと思われます。ちなみにナッサウ伯エルンスト=カシミールはその長さについて、「閣下はこの上なく苦悩して」と、どストレートなフランシスの「slow」よりは若干オブラートに包んで表現しています。
決戦当日の朝、騎兵に次いで真っ先にエイゼル川を渡った歩兵もイングランド連隊でした。まだ渡るというより泳ぐというほど水位が高く、ずぶぬれになって対岸に着いた兵たちは、着替えをしようと服を脱ぎ始めました。
「着替えはとっておけ。今夜、乾いた服で寝られるようにな。」 *4
一刻を争う状況だったこと、まだ後ろに渡河中の部隊が居たことから、何よりも部隊の移動と展開を優先させたがゆえの命令でしたが、この状況下での命令としてはかなり粋なものです。もっとも、実はこの2文の間に「服なんて不要になるかもしれないし…いや、」と言い直したりしてるんですが。
そして両軍が陣容を整えると、総司令官のもとに集まっていた将軍たちはそれぞれの持ち場へ向かいました。その時、ヴィアーはマウリッツにこのように声をかけています。
「私の出番が来たようだな。いつも以上の働きをしろというんだろう?」 *4
結果として、最も長い時間激戦区で戦い続けたのは、フランシス率いる前衛のイングランド連隊とフリースラント連隊でした。戦いの翌日マウリッツはイングランド女王エリザベスに宛てて、今回の勝利は何より陛下の将軍の功績によるものである、と書き送っています。
ナッサウ伯フレデリク=ヘンドリク
Thomas Willeboirts Bosschaert (1650) In Wikimedia Commons ニーウポールトの戦いのマウリッツとフレデリク=ヘンドリク(ハウステンボス宮オランイェザールにある壁画のひとつ)
ナッサウ伯フレデリク=ヘンドリク
オランダ軍の攻囲戦には通常、たくさんの見学者が同行しました。外国の貴族の若者が勉強のために来ていることが多く、場合によっては女性や子供までいたほどです。今回の遠征にも何人かの貴族が同行していました。中でもいちばんの大物は、いずれも二十代のホルシュタイン公ヨハン=アドルフ(デンマーク国王クリスチャン四世末弟)、アンハルト侯ヨハン=エルンスト(アンハルト侯ヨアヒム=エルンストの六男)の2人です。また、彼らの話し相手も兼ねて、従軍年齢に満たない少年たちも何人か含まれていました。たとえば、総指令マウリッツの弟フレデリク=ヘンドリクや、その母方の従兄弟のコリニー兄弟(アンリとガスパールの2人)などです。
全軍が渡河を終え、補給船が到着すると、マウリッツは彼ら客人たちや連邦議会の議員たちなどの非戦闘員を、この船に乗せてオーステンデに移送することにしました。正直足手まといでもあり、とくに王弟ランクの貴族に万が一死なれでもしたら、後々面倒でもあるからです。また決戦を目前にして、マウリッツ以下将軍や将校たちは、おそらくオランダ軍が壊滅すること、自分たちも戦死するであろうことを覚悟していました。マウリッツは自分が戦死したとしても、オランダが父ウィレムの血統を継ぐ指導者を持ち続けることができるようにと、弟のフレデリク=ヘンドリクにも補給船で逃れるよう言い聞かせます。しかしフレデリク=ヘンドリクは、
「僕は残ります。生きるも死ぬも、兄上とご一緒させてください」 *5
とひざまづいて涙ながらに訴え、マウリッツの手を離そうとしなかったので、仕方なくマウリッツは「自分の目の届く場所にいること」を条件にしぶしぶ従軍を許しました。
ところがこれがほかの客人の義勇心にも火を点けてしまい、「若い弟君が残るのに、我々だけ逃げるわけにはいかないだろう」と、全員が戦場に残ることになってしまいました。結局彼ら全員を「目の届くところ」に置いて気にかけていなければならなくなったため、マウリッツにとっては、この非常事態下で余計な仕事が増えてしまったことになります。
Bartholomeus Willemsz. Dolendo (1600-1610) In Wikimedia Commons 左下のほうに鎧を着た客人たちとその全員の名前が書き入れられています
もっとも戦闘が始まるとそれどころではなくなり、見通しの悪い戦場でマウリッツは、常に移動しながら刻々と変わる戦況を確認し各所に指示を与えていたため、フレデリク=ヘンドリクたちのほうがマウリッツを見失わないように追うのが大変だったようです。彼らは全員、鎧を着用して身を守るようマウリッツに指示されましたが、このとき初めて戦場で全身鎧を着用したフレデリク=ヘンドリクは、砂地で馬を駆るにも難儀したことでしょう。
このエピソードは、ニーウポールトを扱った資料の多くに紹介されています。内容だけ見ると出来過ぎの感もあり、個人的には最もマユツバ度が高いエピソードだと思っていました。が、初出時の出所から判断するに、むしろ逆に最も信憑性が高いもののひとつです。当時から人気の高いエピソードだったらしく、若干わざとらしい兄弟図も、当時からロマン主義時代にかけてたくさん描かれています。
戦いはオランダの勝利に終わったので結果オーライでしたが、もし逆の結果であれば、オーストリア大公アルプレヒトが当初目論んだように、兄弟揃って捕虜となって、イザベラへの手土産にされてしまった可能性もありました。
南ネーデルランド執政夫妻
Juan Pantoja de la Cruz (1599) In Wikimedia Commons 亡き父王フェリペ二世のミニアチュアを持つイザベラ
オーストリア大公アルプレヒト/イザベラ=クララ・エウヘニア
フレデリク=ヘンドリクのそんな顛末があって、オランダ軍将校全員と客人たちのほとんどが残ることが決定しました。スペイン軍総司令官アルプレヒト大公はその知らせを受け取ると、
「捕虜はマウリッツとその弟の2人のみで良い。残りは皆殺しにせよ。」 *1
と全軍に向かって命じました。が、なぜ「一人残らず皆殺し」ではなく、この2人だけ捕虜にするのでしょう。ひとつには、大公の妻であるイザベラが、戦地に向かう夫君に「戦利品」を所望したためです。
「あのマウリッツをわたくしの目の前に引き据えて、無様に吠える様を見てみたいものですわ。」 *1
イザベラは2年前に亡くなったスペイン前国王フェリペ二世の王女で、父王の最晩年までその側で公務の手伝いをしていました。最も父王に近しく、その考えに触れていた人物といえます。父フェリペ二世としては、やっとのことでウィレム沈黙公を片付けたと思ったら、あろうことかその息子があちこちで反攻を続けているわけで、最期まで苦々しく思っていたに違いありません。またイザベラはちょうどマウリッツと同世代であり、互いに父親の遺志を継いでいる者としての対抗意識もあったのかもしれません。
いずれにしてもアルプレヒト自身も、彼ら2人を捕虜としてスペインまで連れて行くつもりでした。「祖国の父」などと呼ばれる男の息子たちを戦死させて下手に英雄化させてしまうよりも、彼らの長兄のフィリップス=ウィレムよろしく、反乱軍の手の届かない本国で監視下に置いておくほうを良しとしたのでしょう。
ナッサウ伯ローデウェイク=ヒュンテル
Jacob de Gheyn (II) (1603) ニーウポールトで捕獲されたスペイン軍馬 In Wikimedia Commons
ナッサウ伯ローデウェイク=ヒュンテル
フランシス・ヴィアーと並んで、ニーウポールトの立役者の一人。戦闘中も彼とその部隊はかなり酷使されましたが、戦後のエピソードも有名です。
スペイン兵が敗走したのち、戦場に置いていかれた戦利品の中から、ローデウェイク=ヒュンテルは一頭の白馬を捕獲しました。この白馬はアルプレヒト大公がブリュッセル入城の際に乗っていた、1000クラウン以上(3000万円前後でしょうか)もするアンダルシア産の良血馬で、すぐに司令官のマウリッツに献上されたことになっています。が、本国に残っている長兄のウィレム=ローデウェイクに、
「大公の白馬を捕獲しました。本当は兄上に差し上げるつもりだったのですが…」 *2
と書き送っているところをみると、どうやら馬マニアのマウリッツに横取りされてしまったようです。兄のエルンスト=カシミールも「閣下はあまりにご執心で、ご自分の厩舎に入れたいとおっしゃった」と明記しています。また長兄のウィレム=ローデウェイクからの返事に、「閣下がメンドーサ提督を、お前個人の捕虜としてくれたことはとても喜ばしい」とも書いてあるので、馬をめぐってマウリッツと何やら裏取引までしたのかもしれないと邪推したくなってしまいます。しかしこのことでローデウェイク=ヒュンテル個人に身代金が入り、2年後彼はそれを持参金に結婚することができました。ウィレム沈黙公の死から16年も経ちますが、それでも一族の結婚資金に事欠くほど、まだまだナッサウ家の財政状況は好転してはいなかったようです。
ローデウェイク=ヒュンテルは別のイタリア産の黒毛馬をわざわざ購入して、ウィレム=ローデウェイクに贈ることにしました。エルンスト=カシミールも執政イザベラの白い乗用馬を捕獲しましたが、もちろんこちらもマウリッツに取られてしまっています。
ちなみにこの馬について聞きつけた英国のエリザベス女王も、自分の馬車に欲しがっていました。また、ニーウポールト以降の騎馬のマウリッツを描いた絵画にはほとんどこの馬が描かれており、当時この白馬を所有していることは相当なステイタスとみなされていたようです。
ナッサウ伯ウィレム=ローデウェイク
Hermann Plüddemann (1855) ゲルハイムの戦い(歴史画) In Wikimedia Commons
ナッサウ伯ウィレム=ローデウェイク
ウィレム=ローデウェイクはこの遠征では留守番部隊でした。そのためもちろんこの戦いの勝利については手紙や急使によってしか知りようがないのですが、最初に受け取ったのは7/2当日付と7/5付の、マウリッツの極限までに事務的な2通の手紙のみ。その後2週間程度、マウリッツも弟2人も多忙すぎて手紙を書けず、ウィレム=ローデウェイクはドイツの父に詳細を知らせるためには情報が少なすぎてやきもきしていたようです。そんな父宛の手紙の中の一文。
「ちょうど300と2年めです。この戦いが行われたまさに新暦7月2日に、我らが皇帝アドルフは、オーストリア公アルプレヒトに追われたのです。」 *2
これは1298年の「ゲルハイムの戦い」のことを指しています。ゲルハイムの戦いはナッサウ家唯一の神聖ローマ皇帝(正式にはローマ王)ナッサウ伯アドルフが宿敵オーストリア公に敗れた歴史的な戦いで、たまたま302年前の同じ日のことでした。しかも、アドルフを戦死させた相手はオーストリア公アルプレヒト一世、ニーウポールトでの敵将オーストリア大公アルプレヒト七世とまったく同じ名前でもあります。300年越しの恨み(日本でいう7代先どころじゃないですね)ですから、この日にちに咄嗟に反応するのも、ドイツ本家の長男としては当然のことでしょう。
しかし今回に関しては、アルプレヒト大公は戦死するどころか数日後には軍を立て直しており、その後フランドル遠征自体も失敗に終わっています。八十年戦争を通してナッサウ家が一貫して休戦に反対したのは、ハプスブルクに対しての完膚なきまでの勝利(=南北ネーデルランドの統一)を追求していたためかもしれません。
ジョン・オーグル
Unknown (1600-1605) ニーウポールトの戦い In Wikimedia Commons イングランド軍の位置がわかりやすい版画
ジョン・オーグル
ジョン・オーグルはフランシス・ヴィアー率いるイングランド第一連隊の副連隊長。フランシスは実績こそ超一流でしたが、その極端な性格から、信奉者も敵もやはりそれぞれ両極端に大勢いました。オーグルはその前者の筆頭です。連隊長であるフランシスの最も近くである副長の位置にいたので尚更です。
戦いの「前」までのフランシスについては上に書いたとおりです。その後、戦いの最前線でマスケット銃に脚を2ヶ所貫通されながらも指揮を執り続けていたフランシスは、終盤にはとうとう落馬して馬の下敷きになってしまいます。通りすがりの同国人たちが引きずり出してくれなければ捕虜になってしまうところでした。このイングランド人というのが、オーグルのほか、マウリッツの客人の一人ロバート・ドルリー卿とその従者のハイアムの計3人です。フランシスは自身の回想録の中ではオーグルには一切触れず、ドルリー卿とハイアムだけを挙げています。その理由を、オーグルは「隊長が私に言及していないのは別段不思議ではない」として、こう記しています。
「隊長の血は相当に長い間私の衣服に残っていたし、私はそれを着るのにふさわしいと思っていたため、その時私が隊長とそう遠くない所にいたというのは明白だったからである。」 *4
…要は、フランシスの血の染みた服を、敢えて公衆および本人の前で長いこと着続けていたわけで、わざわざ書き残す必要もないほどの周知の事実だったということです(どちらかというと、フランシス的には書き残したくないほどドン引きだったんじゃないかと思うんですが…)。しかも、明らかにフランシスの回想録を読んでいることが前提の内容ですが、回想録は出版を目的としたものではなく、死後に発見された多分に私的な日記であり、オーグルがそれにどうやってアクセスしていたのかも謎です。
こういう感性が当時めずらしくなかったのかどうかはわかりませんが、崇拝もここまでいくとちょっとアレだな、と思ったので、ついでに紹介しておきました。
ナッサウ伯ユスティヌス
Jan Lievens (1627-1630) コンスタンテイン・ホイヘンスの肖像 In Wikimedia Commons
ナッサウ伯ユスティヌス
ニーウポールトの戦いから29年後、70歳になりレイデンで隠居生活を送っているユスティヌスは、異母弟フレデリク=ヘンドリクの秘書コンスタンテイン・ホイヘンスの名付け親でもあり、彼と非常に懇意にしていました。1596年生まれのホイヘンスは、もちろんニーウポールトの戦いをリアルでは体験できない年齢です。1629年、ちょうどスヘルトヘンボスで主人のフレデリク=ヘンドリクが攻囲戦をしている時期、どうやらホイヘンスは、「ニーウポールトってどういった戦いだったんでしょう?」とユスティヌスに質問したようです。
「故フランシス・ヴィアー卿の指揮のもと、絶妙なタイミングで戦いは始まりました――そしてやはり今は亡きローデウェイク=ヒュンテル伯の騎兵突撃が、先のオランイェ公最大の名誉と華々しい勝利に貢献したのです。」 *2
当時は誰の目から見ても疑いなく最も偉大な勝利であり、今度ハーグでお会いする機会があればもっとお話しましょう、とユスティヌスは最後も比較的短く締めくくっているので、自分でも老人の繰言的な自覚はあったのでしょうか。逆にいえば、ユスティヌスがこの戦いをそれだけ大事な思い出としている、ともいえるでしょう。マウリッツは4年前に死去したばかりですが、ユスティヌスが挙げた他の2人の将軍はいずれも20年以上も前に死亡しており、彼ら将軍たちや、ニーウポールトの戦いそのものまでが忘れるままにされることが少し淋しかったのかもしれません。
リファレンス
-
- Motley, “United Natherlands” *1
- Prinsterer, “Archives” *2
- Duyck A., “Journal” 3*
- Firth, “Tracts” *4
- Le Petit, “Chronique” *5