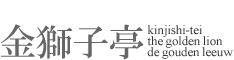オランイェ公ウィレムの最期のことば (1584) In Wikimedia Commons
「反乱」や戦争などの動乱期、その渦中の人物は、処刑、暗殺、戦死、などいろいろな最期を遂げます。かといって、そんな時代とはまったく関係がないかのように、病死や天寿を全うする人もいます。英雄とされる人々の死は、のちにプロパガンダに利用されるため、ドラマティックに扱われることも少なくありません。
ここでは、そんな人々の最期のことば(とされるもの)を、時系列順に集めてみました。あくまで「とされるもの」であり、真偽のほどはこの際二の次にしてあります。日本語訳の存在しているもののみピックアップしました。
エグモント伯・ホールネ伯
Louis Gallait (1859) エグモント伯・ホールネ伯の葬儀(歴史画) In Wikimedia Commons
いずれも処刑:1568年6月5日
丸山武夫訳/シラー 『オランダ独立史 下』 pp.227-229
「ユリアン・ロメロにむかつて助命の希望はないかと、もういちどたづねた。」
シラーの『オランダ独立史』の記述。処刑の日、エグモント伯は処刑台からの演説を希望しますが、騒乱のもとになってはいけないと司祭から止められます。エグモント伯は国王を信じていたため、この処刑が取りやめになるのではないかと待ち続けました。最後にもういちど上記のように訊ね、希望がないと確信し、処刑台にひざまづきました。
「そばにゐた一人に、友人の死骸であるか、とたづねた。」
エグモント伯が処刑された直後、ホールネ伯が処刑台に連れてこられます。「彼はこの友人よりも氣象がはげしく」、王に対して呪いのことばを叫び続けていましたが、やはり司祭に説得され静かになりました。彼の場合は、先に処刑された友人の姿を見ることによって、自分にも希望がないことをより確信したはずです。
ウィレム沈黙公
Wilhelm Lindenschmit (1879) オランイェ公ウィレムの暗殺(歴史画) In Wikimedia Commons
暗殺:1584年7月10日
瀬原義生訳/ウェッジウッド 『オラニエ公ウィレム』 pp.352-353
「主よ、わたしの魂を憐れみ給え、主よ、哀れなわたしの人民を憐れみ給え」
最も有名な台詞で、ほんとうにいろいろなところで引用されます。早くも暗殺の数日後には、息子のマウリッツが書簡に引用しているくらいです。ウィレムは自宅の食堂を出て、階段下の廊下で撃たれたわけですが、この時駆けつけたのは、使用人のほかは妹・妻・娘など身内の女性ばかりでした。ので、「後からつくられた」可能性がもっとも高いことばだともいえますが、最後まで「人民」に言及しているのは、生涯滅私奉公し続けてきたウィレムを端的にあらわしているともいえるでしょう。
暗殺当日の連邦議会議事録 (1584/7/10) In Wikimedia Commons ウィレムのことばは右ページ2段落め
ソースは、(1) ウィレムの長女マリアが叔父ヤン六世に宛てた手紙 (2) 外交官が英仏国王に宛てた外交文書 (3) 暗殺当日の連邦議会議事録、など複数残されています。冒頭の画像は、ウィレムの最期のことばとして、連邦議会の議員が書き留めた議事録(蘭語)の当該部分に下線を引き、その余白におそらくコルネリス・アールセンによって仏語訳が書かれたといわれるもの。が、オリジナルのことばが、独語か、仏語か、蘭語か、何語で語ったのか特定はされていません。
2012/4/1-7/1 デルフトのプリンセンホフで特別展 “Cold Case: Willem van Oranje” 開催。「ウィレムの死」に医学的・科学的に迫った分析結果など展示していたそうです。詳しい記事はこちら。
“Laatste woorden van Willem van Oranje” Is Geschiedenis(蘭語)
上記の最新研究からの補足。
19世紀の研究者からも既に疑問の呈されていたこのことばですが、現代の法医学的にも、ことばを発する間もないほどの即死だったのでは、という見地が示されているようです。また、仮にことばを発することができたとしてもそれはほんの短い間――せいぜい「神よ」と呟く程度――なので、唯一それを聞き取れる可能性があるのは側に居た盾持ちの少年ひとりだけであり、彼が駆けつけた議員たちによって圧力じみた聴取を受けた可能性もあります。
少なくともその日の議事録にはすでにこのことばが書かれています。盾持ちの少年か、侍医か、議員か、いずれかの段階で当日内に「つくられた」ものかと思われます。
フィリップ・シドニー
John Cassell (1865) シドニーの死(歴史画)脚の負傷と水がわかりやすいバージョン In Wikimedia Commons
戦傷による病死:1586年10月17日
日本シェイクスピア協会編/玉泉八州男『新編シェイクスピア案内』 p.19
「お前のほうが必要のようだ。」
オランダ史という限定をはずせば、おそらくウィレム沈黙公以上にその最期の様子が有名なのは、イングランドの詩人・軍人のフィリップ・シドニーです。伯父レスター伯に従ってオランダで義勇軍として戦っていて、ワルンスフェルトの戦いで脚に致命傷を受けました。周囲の者がシドニーに水を差しだしたとき、自分以上に重傷な兵士に向けて語ったことばです。
もっとも、シドニーの死はこのときの傷に起因した敗血症によるもので、その1ヶ月ほどの間にたくさんの知人が見舞いに訪れており、ほんとうの「最期」の台詞は最後まで側にいた弟ロバートに語ったものになります。
詳しい様子は「ワルンスフェルトの戦い」参照。
ヨハン・ファン・オルデンバルネフェルト
Jan Luycken (1650-1700) オルデンバルネフェルトの処刑 In Wikimedia Commons
処刑:1619年5月13日
朝倉純孝『オランダ黄金時代史』 p.25
「諸君、わたしが反逆者であると信じないでほしい、わたしは誠実に敬虔によき愛国者として行動した、そして愛国者として死ぬ」
いくつか日本語訳のある中で、もっとも簡潔なものを選びました。エグモント伯・ホールネ伯と違い、オルデンバルネフェルトは処刑前に演説の機会を与えられたようです。
ところでスタットハウダーに認められた権限のうち、重要なもののひとつに「既決囚の恩赦」がありました。死刑判決の5月12日から翌朝の執行までの間、マウリッツの部屋には一晩中灯りがついていました。しかしオルデンバルネフェルトの妻子や友人たちは、反逆者であると認めることになるとして、助命嘆願を行いませんでした。
1623年、オルデンバルネフェルトの息子たちによるマウリッツの暗殺未遂事件が起こります。このとき、死刑判決を受けた息子の助命嘆願に訪れたオルデンバルネフェルトの妻マリアに対して、なぜ4年前に夫に対してもそうしなかったのかとマウリッツは詰り、結局この嘆願も受け入れませんでした。
ここに挙げた版画は半世紀以上後に描かれたものですが、3本のリボンのように見える吹き出しに最期の台詞が書き入れられています。
ロス=バルバセス侯アンブロジオ・スピノラ
Diego Velázquez (1635) ブレダの開城 In Wikimedia Commons
病死:1630年9月25日
アルトゥーロ・ペレス・レベルテ /レトラ 『アラトリステIII ブレダの太陽』 p.114
「名誉も名声も失って私は死んでゆく…。財産も名誉も、何もかも奪われてしまった…。」
私財を投げうち、破産してまで、イタリア人であるにもかかわらず、スペインやカトリックのために30年間も戦い続けた彼の原動力は何だったのでしょう。確かにスピノラ一族には聖職者も多いのですが、アンブロジオの信仰心が人一倍篤かったというわけでもなさそうです。というのも、スピノラの臨終の枕元にいたのはジュール・マザラン(リシュリューを継ぐ、後のフランス宰相)だけだったといわれているので、このことばを伝えたのもマザランということになりそうですが、枢機卿であるマザランが伝えたことばにしてはあまりにも世俗的な感があります。富でも信仰でもないとすれば、残るものは名誉だけだったのかもしれません。
残念ながら、スピノラは存命中に報われることはありませんでしたが、死の5年後にベラスケスによって描かれた『ブレダの開城』によって、今日までその名誉と名声を伝えています。
リファレンス
各項目参照。