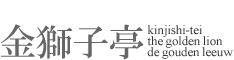Peter Paul Rubens (17th century) ある司令官の肖像 In Wikimedia Commons
八十年戦争時代(16-17世紀)の貴族の男性はどのように育っていったのでしょう。中世以来実はあまり変わらず、大体下記の三段階を経て成人します。次男以下、長男以外の場合は、カトリックの家系だと聖職者の道に放り込まれることも多いのですが、ここではプロテスタント系に多いキャリアを挙げました。
一般的に「ペイジ」は「小姓」や「騎士見習い」、「エスクワイア」は「従騎士」と日本語訳されるようですが、このサイト内ではいずれも、講談社オランダ語辞書の記述「近習」「盾持ち」に合わせました。「小姓」はどうも日本史(時代劇)のイメージが強すぎるのと、16世紀以降には既に「騎士」の用語は適さないと判断したためです。ちなみに、オランダ語では「ペイジ page」は同じですが、「盾持ち」は文字どおり「盾(を持つ)少年 schildknaap」です。
この段階を経て最終的に17-18歳で成人とみなされます。中世のような「少年を騎士に叙勲」という儀式はほとんどないのではないでしょうか。(騎士身分ではない者を騎士とする儀式はあります)。オランダ軍では、基本的に18歳が従軍年齢とされていました。
幼児期
左:Unknown (after 1580)/中:Unknown (1604)/右:Unknown (1608) In Wikimedia Commons
幼児期は性別の区別なく育てられます。着ているものも男女同じで、左の絵はナッサウ伯マウリッツの四妹エリーザベト、中は次男のローデウェイクです。言われなければどちらがどちらか区別がつきません。大体今の学齢と同じくらいの6-7歳で、男子は大人と同じ格好になります。右がマウリッツの庶子ウィレム、7歳時点です。
ペイジ(近習)
Jean de Saint-Igny (17th century) アンヌ・ドートリッシュ騎馬像 In Wikimedia Commons
着るものが変わったくらいの6-7歳の頃から、大体14-15歳くらいまで、家を出て「近習」として他の貴族(基本的には自家よりも位が上の貴族)に仕えます。カルヴァン派の場合は、10歳くらいまではジュネーヴやハイデルベルクなどの学校で初等教育を受ける場合もあります。
画像はルイ十三世妃アンヌ・ドートリッシュ。仕える貴族は男性とは限らず、女性に仕えることもあります。着替えや身支度の手伝いをしたりはしますが、召使や下働きではないので、当人の着ているものも小奇麗です。
エスクワイア(盾持ち)
Charles Le Brun (1655-1661) 大法官セギエ In Wikimedia Commons
14-15歳になると、近習時代よりも、より主人の身の回りの世話をしたり、OJT色が強くなってきます。ただ、あまり17世紀当時の文献ではEsquireの単語は出ずに、ずっとPageと呼ばれ続けている気もします。あまり区別がはっきりしていないのかもしれません。大人との区別は、ひげの有無がいちばんわかりやすいです。
画像は、ルーブル美術館にある有名な絵画。これは晩年に近い頃ですが、大法官セギエは若い頃にはリシュリューの腹心として、対オランダ外交にもちょくちょく名前がでています。(おかげで『三銃士』ではリシュリューの部下のしみったれた悪役…)。画面内に見えるだけでも6人の盾持ちを揃えていますが、傘が2つあることをみても、向こうにもう1人いるでしょうね。
盾持ちの仕事
Paris Bordone (16th century) 軍装の男性と2人のペイジの肖像 In Wikimedia Commons
ウィキペディア英語版に、盾持ちの仕事が列記してあったので、簡単に訳しておきます。
“Squire” In Wikipedia, the free encyclopedia
- 主人の鎧、盾、剣を運ぶ
- 主人が捕らえた捕虜を拘留する
- 捕虜となった主人を救出する
- 主人が死亡した場合は名誉ある埋葬をする
- 折れたり落ちたりした主人の剣を交換する
- 傷ついたり死んだりした主人の馬を交換する
- 主人に甲冑を着せる
- 主人の旗持ちをする
- 主人の命を守る
- 主人の馬の世話をする
- 馬上試合や戦争の際に主人に同行する
- 主人の鎧や武器の状態を常に最良に保つ
ただ、このリストにあるのはどちらかというと中世の騎士を想定した、しかも非常時(戦時)のことですね。
従者と召使
Anton Domenico Gabbiani (circa 1684) メディチ家の4人の召使 In Wikimedia Commons
ついでにちょっと横道。従者や召使は、近習や盾持ちとまったくもって別物です。『三銃士』を挙げたのでついでにメモしておきました。たとえば三銃士とダルタニャンにはそれぞれ個性的な従者が一人ずついますが、彼らは貴族ではなく給金で雇われた被雇用者で、少年でもなくおっさんです。主人より年上だったりもします。近習や盾持ちを持てるのは基本的には大貴族だけですが、それ以外の貴族や軍人も、身の回りの世話をする者が必要な場合、このように従者を個人で雇っていました。もちろん、大貴族たちも近習や盾持ち以外に召使・従者・奴隷などを使用しています。
なお、女性(侍女等)についてはまた別なので、この記事上は男性のみを取り上げています。
『アラトリステ』では、主人公アラトリステは友人の息子のイニゴを自分の従者にしています。しかしそれもあくまで彼が成人するまでのことです。これはある意味、教育がてら盾持ちのように使っているともいえます。
私設秘書
Thomas de Keyser (1627) コンスタンテイン・ホイヘンスと秘書 In Wikimedia Commons
私設秘書は「個人の被雇用者」という意味では従者に分類しても良いかと思いますが、中でも最も上位クラスといえます。議員や外交官などほかに官職や身分をもち、その上で秘書を兼任していることも多いです。画像はコンスタンテイン・ホイヘンス。ホイヘンス自身がオランイェ公フレデリク=ヘンドリクの私設秘書ですが、画像ではさらに彼自身の秘書も雇っています。
黒人従者
Paul van Somer (1617) ジェームズ一世王妃アンIn Wikimedia Commons
黒人の場合、「エスクワイア」の項に挙げた「軍装の男性と2人のペイジの肖像」のように、少年の従者が圧倒的に多いです。仕事は基本的にペイジと同じで、主人の身の回りの世話をしたり、馬丁として描かれている姿もよく見かけます。お仕着せもほぼペイジと同じ上質のものを着ています。
ペイジとの絶対的な違いは、彼らが奴隷貿易で売買された「所有物」であるということです。「見習い」のペイジは成長すれば一人の貴族として自分もペイジを持つことができますが、黒人従者の場合はそれは叶いません。ただ、主人の信頼が篤ければ、アン王妃の画像のように、成長しても従者として仕え続けることができます。主人と共に華やかな場所への出入りも多くなるため、良い身なりをさせられています。
宮廷道化師
Giacomo Vighi (circa 1572) サヴォイア公カルロ一世エマヌエーレと小人 In Wikimedia Commons
この時代だととくに宮廷小人が画家によってよく取り上げられています(ベラスケスの「ラス・メニーナス」や「道化師セバスチャン・デ・モーラ」などが有名)。いわばお抱え芸人で、「主人を楽しませること」のみが仕事であり、そのためであれば、主人に向かってどんな無礼な台詞を吐いても良い唯一の存在ともされています。が、所有物であることには変わりがなく、王侯同士の贈り物にも頻繁に使われます。
DVD「もうひとりのシェイクスピア」でも、芝居をプレゼントされたエリザベス一世が、小人に向かって「贈り物というのはあなたのことなの?」と話しかけるシーンがあります。
従者
Thomas Rowlandson (18th century) 将校とその従者 In Wikimedia Commons
ちょうど時代の合う絵が探せなかったのですが、この項目の冒頭に挙げた『三銃士』の例のように、貧乏貴族や雇われ将校などの個人が雇っている従者はこんなイメージです。主人(独り身だとだいたいは街中のアパートに賃貸で暮らしてたりしています)の家に住み込みで、従者の人数にもよりますが、基本的には家事一般すべてこなさなければなりません。戦争ともなれば戦地まで鍋釜背負ってついて行き、荷物持ちから煮炊きの世話までおこないます。
主人との相性が良くなければなかなかやってられない仕事でもあります。が、あくまでも報酬をもらっての契約なので、所有物たるところの奴隷と違って辞める自由はあります。主人の側でも、給金が払えなくなったら解雇したり、必要な時期だけ有期で雇ったりという調整ができます。また、これも『三銃士』のように、主人同士が仲が良いとその従者同士も仲が良かったり、協力や分業をすることも可能です。
その他下働き
Marten van Cleve (circa 1565) 厨房内部 In Wikimedia Commons
ここまでは、主人と日常的に直接コンタクトのある(=個人として名前を認識されているであろう)従者について挙げてきました。間接的に雇用されている下働きは、その働く場所、主人の身分によって職種も内容も様々であり、ここでは取り上げません。画像はそれなりの規模の屋敷と思われる厨房の一場面。
リファレンス
記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。
- 佐藤弘幸『図説 オランダの歴史』、河出書房新社、2012年
- 桜田三津夫『物語 オランダの歴史』、中公新書、2017年
- 森田安一編『スイス・ベネルクス史(世界各国史)』、山川出版社、1998年
- 栗原福也「十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国 二 ネーデルラント連邦共和国」『岩波講座 世界歴史(旧版)<15>近代2』、岩波書店、1969年
- ウィルソン『オランダ共和国(世界大学選書)』、平凡社、1971年
- ヨハン・ホイジンガ『レンブラントの世紀―17世紀ネーデルラント文化の概観(歴史学叢書)』、創文社、1968年