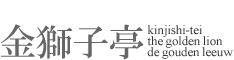Henri Motte (1881) 「ラ・ロシェル攻囲戦」(部分) In Wikimedia Commons
「オランダのロマン主義」から記事を分割しました。ロマン主義歴史絵画を独断と偏見で、ただひたすら並べていきます。
もどうぞ。
八十年戦争期のオランダは別記事にしましたので、同時代の低地地方以外の地域を描いたものをメインにピックアップしました。時代は若干ずれるものもあります。描かれた時代順ではなく、扱っている題材の史実における年号順に並べます。
ロマン主義歴史絵画の特徴は、良く言えば物語性があること、悪く言えばツッコミどころ満載なことです。不必要に若かったり美形に描いてあったり、いろんな部分で盛ってます。はっきりいって笑えるものも多いです。探すといくらでもあるうえ、管理人が19世紀人たちのやりすぎ感や妄想感が大好きなので、発見しだい多分どんどん増えます。
すべてウィキメディア内パブリックドメイン絵画の埋め込みHTMLソースを利用しています。ぜひクリックして拡大画像で見てください。
2014年にリヨンでロマン主義歴史絵画を集めた特別展を開催していたようです。Wikimedia内にも特設ページがあります。
L’invention du passé. Histoires de cœur et d’épée en Europe, 1802-1850
ここで紹介したものもちらほらありますね。
ギャラリー
Simon Meister (1829) 「アドルフ・フォン・ナッサウの死」 In Wikimedia Commons
1298年。ナッサウ家唯一の神聖ローマ皇帝(ローマ王)、アドルフ・フォン・ナッサウの戦死を描いた絵画。これこそロマン主義の典型。だいたい戦場を描いてるものは、主人公(だけ)が白馬に乗っていたりします。しょっぱなからやりすぎな感じのを挙げてみました。
Wilhelm Walther他 (1871-1876) 『君主の行進』から(部分)「ザクセン選帝侯モーリッツとアウグスト」 In Wikimedia Commons
日本語では『君主の行進』と訳される、ドレスデン城の城壁に飾られたマイセンタイル、100m以上にも及ぶ大作です。ザクセンの歴代君主が順に並んでいます。明らかにモーリッツが群を抜いて(といって良いでしょう)イケメンに描かれています。隣にいる弟のアウグストは、クラーナハの肖像画では兄そっくりなのに、ここでは横顔だし老けてるしなんだか添え物扱い…。他の写真との比較はこちらのWikimediaでどうぞ。
Pierre-Nolasque Bergeret (1808) 「ティッツィアーノの絵筆をとるカール五世」In Wikimedia Commons
1550年代? 宮廷画家ティッツィアーノのモデルをしている最中のカール五世。退屈のあまりのいたずら?
Eduardo Rosales (1869) 「ドン・ファンとの対面」 In Wikimedia Commons
1557年。庶子であるアウストリア公ドン・ファンが、初めて父の神聖ローマ皇帝カール五世に拝謁したシーンを描いた有名な絵画。実際の人物の見てくれがどうだろうが主人公を金髪に描く、「金髪化」の典型。
Pierre-Charles Comte (1864) 「アンナ・デステとギーズ公アンリ」In Wikimedia Commons
1563年。父ギーズ公フランソワの暗殺に復讐を誓う幼きギーズ公アンリ。とその母アンナ・デステの図。ギーズ公はもともと金髪みたいなので、これは「金髪化」の例ではなさそう。
Juan Luna (1887) 「レパントの海戦」 In Wikimedia Commons
1571年。アウストリア公ドン・ファンがらみでもう1枚。ボートのいちばん後ろに乗ってるドン・ファン自身は単なるスペイン風イケメンですが、絵に描いたような(絵に描いてるんだけど)ランツクネヒトたちが海戦に登場してるのが非常に不自然。手前の水色のもさることながら、全身真っ赤のトランペッター2人は海の上でも派手帽子かぶったままなのが超ロマン。
Édouard Debat-Ponsan (1880) 「ある朝のルーヴル宮前」 In Wikimedia Commons
映画『イントレランス』 (1916) In Wikimedia Commons
1572年。「サン・バルテルミーの虐殺」の翌朝を描いた絵。この虐殺を指示した黒幕、母后カトリーヌ・ド・メディシスの見下げ果てたような表情が印象的。のちに、映画『イントレランス』(1916)での「サン・バルテルミーの虐殺」の1シーン(画像下)は、ちょうどこの絵と同じアングルで撮られています。
William Frederick Yeames (1865) 「エリザベス一世とレスター伯」In Wikimedia Commons
1570年代?くらいの年齢でしょうか。四十代になっても少女、的なね。後ろの人の引いてる感じもたまらない。
Pierre-Charles Comte (1855) 「アンリ三世とギーズ公」 In Wikimedia Commons
1570年代後半~1580年代。ギーズ公がらみでもう1枚。御付きの者たちの人数から、右の全身白がギーズ公(その隣の全身赤が弟のギーズ枢機卿)、中央全身黒がアンリ三世とわかります。人気のない国王ってさみしい。
Jean-Baptiste Vermay (1808) 「死刑判決を知らされるメアリー・ステュアート」In Wikimedia Commons
Francesco Hayez (1832) 「死刑判決に抗議するメアリー・ステュアート」In Wikimedia Commons
1586年。同じ場面を描いたものでも、まったく違った捉え方でおもしろい対比ができる2枚。上:従容として判決を受け入れるメアリ と、下:毅然として抗弁するメアリ。周りの女性たちの、よよよ、な感じは共通。
John Seymour Lucas (1880) 「アルマダ見ゆ」 In Wikimedia Commons
1588年。いわゆる「敵艦見ゆ」。中央が総司令官ノッティンガム公ハワード。その左で砲弾を持って何やら説明しているのが、おそらくフランシス・ドレイクです。左端の、海を指差している男性の動きがあからさまにロマン主義ぽくて嬉しい。
Unknown (1904) 『旦那様が火事だ!!』 In Wikimedia Commons
1590年代。新大陸からもたらされた嗜好品のひとつ、タバコ。16世紀末の導入期はとくにイングランド人が好んだようですね。イングランドの探検家ウォルター・ローリー卿がタバコを吸っていたところ、初めて見るその煙に驚いた従者が水をぶっかけた、というエピソードを描いたもの。こういうの個人的に大好き。
Karl Jauslin (19th century) 「エスカラード」In Wikimedia Commons
1602年。サヴォイア公カルロ一世エマヌエーレがジュネーヴ支配を目論んで夜中に奇襲し失敗した図。「エスカラード(梯子作戦)」として有名なこの戦いを、ジュネーヴでは毎年冬に祝っています。オバさんがスープをかけてサヴォイア兵を撃退した、というのがこの勝利の肝ではあるのですが、妙にカッコいいこの絵にはスープも登場しなければ梯子もあまり目立たない感じ。
Sir John Gilbert (1869-70) 「ジェームズ一世の前のガイ・フォークス」In Wikimedia Commons
1604年。「火薬陰謀事件」が発覚し、国王ジェームズ一世の前に連れてこられた主犯のガイ・フォークス。彼を題材にした絵画やイラストはむしろリアルタイムより19世紀以降に描かれたもののほうが多いんですが、ここでは若干コミカルなタッチのものを選びました。
Jean Auguste Dominique Ingres (1817) 「アンリ四世と子どもたち」In Wikimedia Commons
1604年。どこぞの大使がフォンテーヌブロー宮殿の国王の自室にやってきたところ、お馬さんごっこをしている国王一家を発見。この絵の解説にはこんな台詞?もついてます。
- アンリ四世 「大使殿、貴殿にお子はおられるかな」
- 大使 「はい、おります。陛下」
- アンリ四世 「では余が部屋を一周回るまで待ってもらえるね」
Karel Svoboda (1844) 「プラハ窓外投擲事件」 In Wikimedia Commons
1618年。これが描かれてないわけがない、やっぱりあって嬉しいプラハ窓外投擲事件。しかし、投げられる3人全員金髪にしなくても良いのでは…。
Claudius Jacquand (1836/1837)「ルイ十三世に短剣を渡すサン=マール侯」In Wikimedia Commons
1620年。リシュリュー枢機卿の失脚および暗殺を狙った「サン=マールの陰謀」が露見し、国王の御前で観念したサン=マール侯の図。ふてくされ気味なのは、自分に下されるであろう刑を甘く見ているがゆえか。それに対比するような、リシュリューのほくそ笑み方が非常に嫌らしくて良いですね。
Wilhelm Trübner (1882) 「祝福を受けるティリー伯」 In Wikimedia Commons
1622年。ヴィンプフェンの戦いのさなか、ドミニコ会の教会に騎馬で乗りつけ、司祭から祝福を受けるティリー伯。バイエルン公マクシミリアン秘蔵の将軍です。「甲冑を着た修道僧」なんて二つ名はまさにロマン主義の格好の題材。教会内に馬を乗り入れるとかどうなの、と思いつつも、馬までなんだか神妙な面持ち(目つきは悪いけど)。
Henri Motte (1881) 「ラ・ロシェル攻囲戦」 In Wikimedia Commons
1627年。ラ・ロシェル攻囲戦で指揮を執るリシュリュー枢機卿。鎧の上にカーディナルローブ、しかも当時にはありえない、クールすぎる3Dな着こなし。そしてこの防護柵も、現代から見てもさらなる近未来を感じさせ、もはやSF的ともいえる絵画です。
Jean-Léon Gérôme (1873) 「灰色の枢機卿(黒幕)」 In Wikimedia Commons
1620-30年代。リシュリュー枢機卿を登場させたのでついでに。「黒幕」の語源となったジョゼフ神父。カプチン会士…ということで、赤ではなく灰色(本来は茶褐色らしい)のローブを着ていたため「灰色の枢機卿」と呼ばれました。特に日本では『三銃士』の影響でリシュリュー=陰謀を企む悪人、のようなイメージが強いですが、リシュリューの「腹心」と称しつつ本当の陰の実力者はこのジョゼフ神父の方です。
Carl Wahlbom (1853) 「シュトゥームの戦い」 In Wikimedia Commons
1629年。スウェーデンの画家が描いた、まさに陛下超つえー超かっけー、なグスタフ二世アドルフ国王礼賛絵画。敵が意味もなく異教徒風な格好なのもポイント。同じ画家がリュッツェンでの戦死の絵も描いています。
Crofts, Ernest (1884) 「ヴァレンシュタインと三十年戦争の一場面」In Wikimedia Commons
Rudolf Otto von Ottenfeld (before 1913) 「ヴァレンシュタインの野営地」In Wikimedia Commons
1630年前後。ヴァレンシュタインから2枚。徹底的に破壊された村と、左後方にぶらさがってる絞死体。いつでもどこでも誰でも吊るせる環境が三十年戦争の雰囲気を良く出しています。ヴァレンシュタインの場合、暗殺場面を除いても、快進撃というよりはこのように苦悩を感じさせるものが多いですね。
Hans Makart (1861-62) 「パッペンハイムの死」In Wikimedia Commons
1632年。絵の副題「月明かりのリュッツェンでパッペンハイムを発見するティリー」。月明かりというより手元のランタンが懐中電灯に見えて仕方ない。それより何より、ティリー伯のほうが半年ほど先に天に召されていたような。お化け?お迎え?
Carl Theodor von Piloty (1855) 「占星術者セニとヴァレンシュタインの遺体」In Wikimedia Commons
1634年。こちらは暗殺後のヴァレンシュタイン。滅多刺しにされたとは思えないきれいな着衣。血もほとんど出てません。
Karel Javůrek (1879) In Wikimedia Commons「ラインフェルデンの戦いの後、死に瀕した友人を見舞うザクセン=ヴァイマール公ベルンハルト」
1638年。シーンはそのタイトルのとおりなんですが、このときピンピンして見えるベルンハルトも、翌年には病死してしまいます。その要求をエスカレートさせるベルンハルトが邪魔になってきたフランス(リシュリュー)にとっては、なんとも好都合なタイミングですが…。なんて疑念もロマン主義。
Charles Landseer (1845) 「エッジヒルの戦い前夜」 In Wikimedia Commons
1642年。指揮杖を持つリンゼイ伯に反論するプリンス・ルパートを片手で制する国王チャールズ一世の図。と、ワンシーンの静止画なのに、前後のストーリーまでを感じさせる、妄想力想像力に富んだ一枚。
François Joseph Heim (1834) 「ロクロワの戦い」 In Wikimedia Commons
1643年。殿下超つえー超かっけーな絵、フランスの画家によるフランス版。ルイ二世コンデ公(大コンデ:この時点ではアンギャン公)が若干22歳にして、スペインテルシオに引導を渡したといわれるフランス軍の大勝利を描いています。若さ強調のためか、コンデ公も馬も白すぎです。ひげも無いし。
Vilhelm Nikolai Marstrand (1866) 「トルステンソン戦争」 In Wikimedia Commons
1644年。陛下超つえー超かっけーな絵、デンマークの画家によるデンマーク版(ホントにこのパターン探すといくらでも出てくる)。大怪我を負いつつも、自ら艦上で指揮を執り続けるクリスチャン四世。右で屈んでいるのは救急箱持った医者のようです。
Charles Landseer (1851) 「ネイズビーの戦いのクロムウェル」 In Wikimedia Commons
1645年。オリヴァー・クロムウェルとトマス・フェアファクス。クロムウェル(手前)が46歳のオッサンと思えないほどイケメンです。ひげも無いし。右側、ひとまわり下のフェアファクスと同じくらい若いですね。
Eugène Lami (1829) 「少女からバラを受け取るチャールズ一世」 In Wikimedia Commons
1647年頃。こちらは逆に叙情的なモチーフ。裁判にかけられるため虜囚場所に送られるイングランド国王チャールズ一世に、少女がバラ(イングランド王権の象徴)を手渡しています。この後の国王の運命を感じさせて、ちょっと切ない雰囲気です。
リファレンス
- ヒュー トレヴァー=ローパー『ハプスブルク家と芸術家たち』 、朝日新聞社、1995年
- ヒュー トレヴァー=ローパー『絵画の略奪』 、白水社、1985年
- フロマンタン『オランダ・ベルギー絵画紀行―昔日の巨匠たち』 、岩波書店、1999年