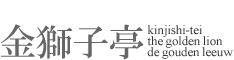after Pieter Snayers (After 1629) 「フランドルの村を襲うスペイン兵」 In Wikimedia Commons
八十年戦争の期間中(1568-1648)、戦っていた当事者って誰でしょう? 陸軍に関しては実は意外にシンプルで、
- オランダ側 = 反乱軍 → オランダ軍
- スペイン側 = フランドル方面軍
といってしまって差し支えないと思います。
スペインのフランドル方面軍は、1567年から始まったネーデルランド地方の「偶像破壊運動」の対策として設立されたので、ほぼ八十年戦争の起点と起源は同じです。オランダ軍は、直訳すれば「諸州軍」です。諸州(States)にどこまで含めるか、その意味をどう取るかでその起点は変わってきます。
- 八十年戦争の起点と同時 1568年
- 第一回連邦議会開催(1572年)/ヘントの和平(1576年)/ユトレヒト同盟(1579年)のいずれか
- オランダ連邦共和国の成立 1588年
1はウィレム一世の挙兵を起点にしたもの、2はそれぞれ「反乱」の重要なステージ(それぞれ関わる州の数が違います)のどれかを起点にするものです。しかし、軍制改革を経て、明らかに1590年以降の軍隊はその性格が違うため、ここでは3を前提とすることにします。
オランダ軍
Pieter Snayers (After 1629) 「スヘルトヘンボス攻囲戦 (1629)」 In Wikimedia Commons
上記の理由により、「連邦軍」とは訳さず、「オランダ軍」(共和国軍)としました。また、それ以前のものを便宜的に「反乱軍」としています。現在のオランダ軍と混同しないためにも、「共和国軍」のほうがベターかもしれません。
内容はほとんど、メイン記事の「オランダの軍制改革」と同じになりますので、ここではおもに兵の調達方法を中心とした補足説明のみとします。
下記については、「オランダの軍制改革」を参照ください。
- 「軍事革命」と「軍制改革」
- オランダの軍制改革の特徴〔制度〕
- 「常備軍」の先駆け
- 給料の定期的な支払
- 訓練と命令系統の統一
- 軍法の制定と規律の強化
- 専門職部隊の創設と武器規格の統一
- 「常備軍」の先駆け
- オランダの軍制改革の特徴〔戦法〕
- オランダ式大隊の編成
- 機動性の向上
- 火力の強化
- 反転行進射撃(カウンターマーチ)
- オランダ式大隊の編成
「オランダ軍」とは名づけてみましたが、その中身は完全に多国籍軍です。オランダ人の若者の場合、陸軍に入るのと同様、船員になる、という選択肢もありました。どちらも命の危険はありますが、一攫千金のイメージのある(実際はそうでもなかったようですが)船乗りのほうが人気がありました。フリースラント、ドイツ、イングランド、スコットランド、フランス、ワロンなど、おもにプロテスタントの各地から傭兵が集められています。これら外国兵全体と比較すると、オランダ兵は少数派ともいえました。たとえば、「ニーウポールトの戦い」のオランダ軍歩兵は、全歩兵のだいたい1/4程度の数にしかすぎません。
傭兵にも大きく二種類あり、長期に渡って常備軍的に雇われたものと、非常時に従来同様スポットで雇われたものがあります。ここでは基本的に「オランダ軍」構成要素である前者を扱います。後者で有名なのは、1622年ベルヘン=オプ=ゾーム攻囲戦の際のマンスフェルト軍やブラウンシュヴァイク軍、一時的に応援を依頼した各都市のワードゲルダーなどです。
階級とトップ・コマンド
Attributed to Pieter Nason (1662-1666) オランイェ公四代の架空肖像画 In Wikimedia Commons
階級図は下記のとおり。サイト内の記述は基本的にこの表に合わせました。
『戦略戦術兵器事典3 ヨーロッパ近代編』の「16世紀における軍隊の指揮組織」図(p.143)に、オランダ共和国軍の項目(最右列)を付け足してみました。太字が実際の文章によく出てくるもので、逆にほかはあまり見かけない印象です。
| 日本語 | 英語 | 役割 | 共和国軍の場合 |
|---|---|---|---|
| 大将 | General | 全兵科を指揮 | Generaal-Admiraal 州総督(Stadhouder)兼任 |
| 中将 | Lieutenant-General | 副指揮官 ※平時は無し |
「元帥」の定義については * 注) |
| 少将 | Sergeant-Magor-General | 戦闘隊形配備責任者 ※平時は無し |
|
| 大佐 | Colonel | 連隊を指揮 | 連隊(Regiment)長 オランダでは事実上Colonelが「将軍」レベル |
| 中佐 | Lieutenant-Colonel | 大佐不在時の代行 | 騎兵大隊(Squadron)長 歩兵についても「オランダ式大隊」(Batallion)指揮権者と思われます |
| 少佐 | Sergeant-Magor | 戦闘隊形配備責任者 | 「オランダ式大隊」(Batallion)指揮権者副官と思われます |
| 大尉 | Captain | 中隊を指揮 徴募担当 | 中隊(Company)長 |
| 中尉 | Lieutenant | 副指揮官 | |
| 少尉 | Second-Lieutenant | 旗手 | |
| 軍曹 | Sergeant | 兵站の管理 | |
| 伍長 | Corporal | 小さな単位部隊を指揮 | |
| 兵士 | Private | 一般兵士 |
* 注) オランダ軍(共和国軍)では、軍の規模が周辺諸国と比べて小さいことと、国軍としての組織が確立していない(未だ傭兵頼りの部分がある)ことから、「元帥」の定義が曖昧です。この時期の神聖ローマ皇帝軍の「Kaiserlicher Feldmarschall」、フランス軍の「Maréchal de Campagne」は慣例に従って「元帥」と訳しました。共和国軍では意味上の「元帥」は「陸海軍総司令官 Generaal-Admiraal」ただ一人のうえ、「Maréchal de Campagne」と「Maréchal de Camp」が混在して書かれていますが、「Lieutenant-General」かつ「Maréchal (en: Field Marshal)」の文言のある人物を暫定的に「元帥」としました。この意味での「元帥」は、陸海軍総司令官の直下にほぼ常時1名体制(第一次無州総督時代は陸海軍総司令官や元帥が一時的に不在だったり、提督がLieutenant-Generaal-Admiraalとして代任するなど変則運用も有)で、17世紀全体を通しても10名に満たないほどに数が限られています。具体的には、共和国軍設立以降の八十年戦争期間中では、ナッサウ=ディーツ伯エルンスト=カシミール(1607-)、ナッサウ=ヒルヒェンバッハ伯ウィレム(1633-)、ブレーデローデ卿ヨハン=ヴォルフェルト(1642-)の3人のみで、それぞれ時期もかぶっておらず、先任が死亡した後に任命されています。「オランダ共和国陸軍元帥リスト(暫定版)」として別に記事を設けました。
オランダ軍で最も特徴的なのが、トップ・コマンドであるGeneraal-Admiraalです。「陸海軍総司令官」と意訳していますが、海軍の指揮は名目上だけで実際は行いません。君主制国家の場合は自動的に君主の役割ですが、オランダ共和国ではこれは州総督(スタットハウダー)と紐づいています。
が、問題なのがこの州総督で、州別に任命されるものであり、「オランダ全州の州総督」は18世紀になるまで登場しません。もちろん州総督は各州レベルでは問題なくトップ・コマンドですが、全州つまり「オランダ軍」全体となると、便宜上多数の州の州総督を兼ねているオランイェ=ナッサウ家の家長がその役割を担います。その問題については、以下に続く各項目で詳述しますが、「無州総督時代」と呼ばれる州総督不在の時代(但し全州に一人も州総督がいない期間はありません)には、オランダ軍全体としてのトップ・コマンドは存在せず、元帥Field Marshalあるいは副指令Lieutenant-General止まり、ということにもなりました。「君主」の居ないオランダに特有の問題ともいえます。
フリースラント兵
Unknown (17th century) フリースラントの法廷 In Wikimedia Commons
上記で、フリースラント連隊を別に書き出してみたのには理由があります。フリースラントも「連邦共和国」の一員ではありますが、やや特殊な扱いです。1594年までに、いわゆる「七州」が連邦を構成することになりますが、そのうちフリースラントとフロニンゲン(北部二州)は、ナッサウ伯ウィレム=ローデウェイクをスタットハウダーに戴いています。あとから加わったフロニンゲンは別としても、「反乱」当初から参加している自負を持ち、もともと言語や文化も違うフリースラントは、とくにホラント州に無条件に追随することを由としない気風があります。残りの五州がナッサウ伯マウリッツをスタットハウダーとしており、連邦全体での軍事行動は便宜的にマウリッツが総指令のかたちをとりましたが、その権限をもってしても、北部二州個別の軍事に口を挟むことはできません。たまたま彼ら二人が兄弟同然に育った従兄弟同士のため、意思疎通や利害調整がそれなりに可能だっただけの話です。
というのも、1590年代から1600年代はじめにかけてのオランダ軍は、常に人員不足に悩まされています。獲得した都市が増えれば国境警備に人員が割かれ、ある遠征で多数の死傷者が出れば、その補充が急務になります。北部で国境警備のために兵が要るといえば、ウィレム=ローデウェイクがマウリッツに依頼し、マウリッツがホラント州議会をはじめ各議会と派兵の折衝をしなければなりません。逆に南部遠征のために兵が要るといえば、マウリッツがウィレム=ローデウェイクに依頼し、フリースラント議会の了承を得て、兵を都合してもらわなくてはなりません。このような件で個人的にやりとりされた書簡はかなりの数があり、「ドイツの諸侯たちにも人員の確保を依頼してみる」とか「市民兵(ワードゲルダー)にとりあえず打診してみる」など、苦労の跡も見られます。
それでもウィレム=ローデウェイクはフリースラントで非常に慕われていたということもあり、これでも良いほうでした。二代後のフリースラント州総督ヘンドリク一世カシミールの時代になると、州総督とフリースラント議会との関係が悪化するため、議会は共和国全体の軍事活動への派兵を議決しなくなります。つまりオランダ軍全体の遠征の際には、フリースラントのトップが自州の部隊を一切持たずに、身一つで参戦する事例もあったわけです。逆に、次代のウィレム=フレデリクは「無州総督時代」の北部三州の州総督でしたが、これら北部自州の軍隊だけは自由になったものの、最後までオランダ軍全体の指揮権、Generaal-Admiraalの地位は得られませんでした。
イングランド兵
Michiel Jansz. van Miereveldt (17th century) ホレス・ヴィアー卿 In Wikimedia Commons
1585年のアントウェルペン陥落をきっかけとした、イングランドとオランダ連邦議会の「ノンサッチ条約」では、エリザベス一世が毎年イングランド兵6,000名の大陸派兵を約束しました。実際、毎年(数のごまかしは多々あれ)イングランド兵が約束どおり送られてきました。彼らは毎年やって来ては、戦争のない冬期になると帰国します。しかしこれも単純な図式ではありませんでした。
たとえばオランダ方面イングランド軍総司令官のフランシス・ヴィアーは、この冬の時期にイングランド国内で、翌年オランダに連れていく兵を自ら徴募しなければなりませんでした。やはりオランダ同様、減数分の補充が必要だったためです。また、この兵の使い道にも、エリザベス女王側から条件がつけられることもありました。1596年は英軍のカディス遠征のため、翌1597年はアゾレス諸島遠征のため、このオランダ派兵用英軍のほとんどが用いられただけではなく、逆にオランダ軍がこれらの遠征のために、イングランドに兵を貸さなければなりませんでした。さらに、1601年以降の「オーステンデ攻囲戦」では、オランダはオーステンデと東南部国境部の二方面作戦を考えていたのですが、「英兵はオーステンデ用にしか用いてはならない」という条件がつけられ、柔軟な運用ができませんでした。
その後1603年のエリザベス女王の死去と、翌1604年の英西による休戦条約「ロンドン条約」によって、「ノンサッチ条約」は効力を失い、国としての派兵は行われなくなります。ただ、新王ジェームズ一世はイングランド人の義勇兵がオランダで戦うことまでは禁止とせず事実上黙認していたため、兄フランシスを継いだ弟のホレス・ヴィアーは、その後も同じように毎年オランダとイングランドを行き来する生活を続けることになりました。
チャールズ一世の時代となってもそれは変わらず、のちにイングランド内戦で活躍するトマス・フェアファクスなどの将校たちは、ホレス・ヴィアーやエドワード・セシル等エリザベス一世時代からの駐蘭軍最古参の将軍の直弟子として、若年期にオランダで義勇軍を経験していることが多いです。
傭兵企業家
Gerard ter Borch (1658-1659) 書き物をする将校 In Wikimedia Commons
「傭兵企業家」というと、三十年戦争期のヴァレンシュタインが有名です。オランダでも規模こそ違うものの、似たような経営手法が各隊長に求められていました。
本来連邦議会は、不公平の生じないよう、自分たちですべての兵の給与を管理するのを理想としています。しかし、ただでさえ急ごしらえの組織である議会がそれを行うのはまず不可能です。そこで連邦議会は、各連隊の連隊長にまとまった金額を渡して、それで独自に自分の連隊を運営することを要求します。つまり、徴募、兵への給与の支払、自分の取り分の配分まで、すべて連隊長の裁量に任せてしまいます。連隊長はさらに自分の隊の各中隊長に、その中から同じようにまとまった金額を渡し、その中隊内での運用は各人の裁量にまかせます。連隊全体に関わる新兵の徴募までは連隊長の責任ですが、中隊レベルに組織されて後は、中隊長個人に責任が移るわけです。これはオランダ兵も、上記のイングランド兵などの長期的に雇われている外国兵も同じです。
もちろんこれは多大なリスクを伴います。連隊長や中隊長がそれぞれ自分の取り分ばかり多くしてしまうこともできます。が、各中隊、そして各連隊の間でも人員不足は慢性的なので、「密猟」と呼ばれる兵の取り合いや引き抜き(ヘッドハント)も常に行われています。兵士同士で、隣の連隊のほうが給料が良いという噂が流れれば、兵が自発的に他所に移ってしまうこともあります。そのほか、武器のデポジット(新兵に武器を貸与し、毎月の給与から割賦でその代金を天引きするやり方)をはじめとして徴募に関わる資金運用に失敗すれば、隊長自身が借金を重ねたり、隊自体立ち行かなくなる可能性すらあります。さらにオランダ軍の場合、非貴族の兵士からでも勤続年数と能力によっては将校になれますから、面倒で部下に丸投げしてしまうと、部下ばかりが成長して自分が追い抜かれてしまう危険性まであります。
もっとも、実際の兵数よりも水増しして給与を申請したり、閲兵のときだけ隣の隊から「見せ兵」としての兵を借りてきて、支払を多く受けるというような詐欺的な手法も行われてはいました。が、一般的に「オランダ軍は給料が遅滞なく毎月きちんと支払われた」といわれるのは、実はこのように、連邦議会のしっかりとした管理徹底のうえに成り立っていたというわけではなく、各隊長たちの自助努力によるところが大きいといえます。
フランドル方面軍
「アラトリステ(3)ブレダの太陽」では主人公はフランドル方面軍として戦います
この時期のスペインはオランダとばかり戦っているわけではありません。イベリア内ではポルトガルやカタルーニャ、地中海においてはオスマン、大陸内でも英・仏・独・伊、さらに新世界やアジアと、正直四面楚歌状態です。オランダにとっては戦っている相手はほぼスペインだけですが、スペインにとってオランダは、この膨大な敵の中のごく一部に過ぎません。それもありここでは、あくまでスペイン軍の中の一部として、「フランドル方面軍」を扱います。
テルシオ
Niccolò Granello (1583-93) 「テルセイラ島の戦い (1583)」 In Wikimedia Commons
防御に長けた「動く要塞」テルシオは、近世スペイン軍の代名詞ともいえる有名な隊形です。八十年戦争でも、「反乱」時代の初期にはその威力を見せつけました。1643年のロクロワで大敗するまでこのテルシオにこだわり続けた、ということを、17世紀のスペインの斜陽の原因とする向きもあります。ですが、その内容を細かく見ると決してそうではないこともわかってきます。
まずはフランドル方面軍の構成を見てみましょう。本国スペイン兵・カタルーニャ兵のほかに、カトリック国ポルトガル、イタリア、アイルランドをはじめとして、ブルゴーニュ、ワロン、ドイツ各地、そして敵国であるはずのイングランド人の兵まで居ます。オランダ軍に負けず劣らず多国籍軍です。八十年戦争の期間全体を通じて、平均60,000人から多いときには80,000人をフランドルで動員できました。オランダ軍が60,000人以上の兵を維持できたのは1609年から12年の休戦を挟んで以降の話で、それまでは20,000人そこそこが関の山だったことに比べると、スペインの底力が感じられる数字です。
かといってこの中でテルシオを組めるのは、実際はスペイン連隊・カタルーニャ連隊・イタリア連隊くらいなものです。これらはスペインの支配地域出身の兵なので、戦地を転々としながらも常に雇われ続け、こちらもある意味常備軍的に機能しました。古参兵が多いのもテルシオの特徴です。古参兵はどこでも大変重宝されたので、費用もかさみました。逆にその他の連隊(アイルランドやワロンなど)は、人数の問題からもテルシオの規模はなく、臨時雇いの色も強かったようです。たとえば「ニーウポールトの戦い」のフランドル軍は、連隊10のうち、テルシオは4だけで、残りはオランダ式大隊にも似た隊形の連隊です。臨時雇いの隊であれば、この時期オランダ式を取り入れていても全く不思議はありません。その意味でも、17世紀に入る頃までには既に、フランドル軍もテルシオだけに頼っていたわけではないことがわかります。
同じくテルシオの場合、「槍一本あれば誰でも陣を構成することができ、訓練も要らない」ので「将校も突撃とだけ叫んでいればいい」と思われがちですが、それも誤解です。低地地方では攻囲戦が主流になるので、そもそも1590年以降、オランダ戦線ではテルシオらしい大型テルシオの出番自体あまりありません。オランダ軍のカウンターマーチが多用されなかった理由と同じです。むしろフランドル方面軍は、パルマ公ファルネーゼやロス=バルバセス侯スピノラのように、クレバーな兵站や攻囲戦を得意とする指揮官を輩出しており、質の面でも決して軍制改革後のオランダ軍に劣るというものではありません。
ロクロワのわずか5年前の1638年、枢機卿王子フェルナンドはテルシオを用いて「低地地方との戦いが始まって以来の大勝」を収めました(カロの戦い)。このときのテルシオは最盛期とくらべると30%-50%程度の人数で組まれた小型のものですが、その分機動力を兼ね備えることとなり、依然として野戦での脅威であったことに変わりはありません。
スペイン街道
フェリペ二世時代の「スペイン街道」 In Wikimedia Commons
上記に挙げた画像が「スペイン街道」です。低地地方で現地調達されるワロン兵やドイツ兵は割合が半分にも満たないので、フランドル軍の大半は、本国スペインやイタリアから移送される必要がありました。イベリア・イタリア両半島から、基本的にはいったんミラノへ入り、(1)サヴォイアまたは(2)オーストリアルートでいったんブルゴーニュまで行き、そこからまた(1)ルクセンブルクまたは(2)ライン川沿いを経由してブリュッセルに至ります。
もちろん船を使う海上ルートもありますが、イングランド船やオランダ船、海賊船がうようよ居る海域ですから、余計な海戦を避けるためにも、非常時以外はあまり使われません。つまりスペイン街道を常時使えるようにしておくのが、スペインにとっては最重要命題のひとつになります。三十年戦争の時期のスペインは、プファルツ、サヴォイア、フランスと、この街道沿いの地を巡って戦うことになります。一度となく封鎖され、海路を使わざるを得なくなったこともあります。
たとえばフェリペ二世がサヴォイア公カルロ一世エマヌエーレに王女カタリーナ=ミカエラを嫁がせたのも、この街道の維持が目的と推測できますし、上述のスピノラ将軍は、1620年にプファルツ地方(ライン川沿い)、1629年以降はマントヴァ継承戦争に投入されていますが、「スペイン街道」の地図を見ればその意図は一目瞭然です。オリバーレス公伯爵は、なにも嫌がらせ(の要素がまったく無くはありませんが)だけでスピノラをオランダから転戦させたわけではないということです。
「軍隊の移動」という目的でスペイン街道が使われたのは1567年のアルバ公のネーデルランド執政就任時です。この時の10000人が最大で、それ以降は2000人から多くて6000人、フルで街道を用いた軍隊の移動は1593年まで12回を数えるのみです。フランスとサヴォイアの反ハプスブルク同盟が理由での制限が繰り返され、17世紀に入って以降は主に物資や糧食の輸送に使われています。1622年以降使われていないとされますが、とくにオーストリア・ラインルートに対するスペイン側からの回復の試みはその後も何度も行われています。
ところでフランドル方面軍は60,000人以上運用できたと書きましたが、実際に一度の野戦や攻囲戦で使えたのは、オランダ側とそれほど変わらずせいぜい20,000人そこそこです。とくに1590年代・1630年代のフランドル方面軍は、フランスとの二方面作戦にもさらされていました。何より国境沿いの守備に割いた人数が多いというのも、オランダ軍と共通しています。フランドル方面軍の場合は200もの国境駐屯地があり、80,000人をそれぞれに単純に割り振ったとしても、1つは400人足らずになってしまいます。場所によっては守備兵が数十名しか居ない駐屯地もかなりあったようです。
給料未払と反乱
After Georg Hufnagel (1617) 反乱を起こしたワロン人傭兵部隊の処刑 In Wikimedia Commons
「反乱」と訳出してしまうと「ネーデルランドの反乱」の「Revolt」と混同してしまいややこしいため、この場合の「Munity」は「反逆」と訳したほうがいいかもしれません。「Revolt」は政治体制などに対する反抗、「Munity」の意味はもっと狭く、待遇に不満を持った兵の集団が上官や軍に反抗することです。殺人や放火などを伴う暴力的な略奪(突発性のある単純な実力行使)は、これ以外のケースでも慢性的に起こりうるため、ここでは取り上げません。(詳細は「八十年戦争期の略奪」へ)。
ここでいう「Munity」は、雇用者側との労使交渉やストライキに近いです。一般的には中隊や連隊、傭兵団などの一定単位の兵員によるもので、その総意のもと交渉の中心となるリーダーがいます。とはいえ決して権利ではなく、最高刑が死刑の重い行為です。
たとえば1600年の低地地方では、あるワロン兵の一団が将校たちを追い出して聖アンドリース砦に立て籠もり、雇い主であるスペイン軍とその場に来たオランダ軍双方と交渉のうえ、オランダ側に寝返りました。(参照:「ザルトボメル攻囲戦(1599)」の「聖アンドリース砦攻囲戦(1600)」/「乞食党のはなし」の「新乞食」)。よりまともに給与を与えてくれるほうを見定め、価格交渉によって他国へ丸ごと自分たちを売り渡したわけです。
さらに物騒になれば、将校や隊長を人質にして交渉材料にすることも充分考えられますし、逆に失敗すれば、鎮圧や粛清の憂き目にも遭います。交渉が成功した場合でも、リーダーなど数人が見せしめのために死罪になることもあります。ここに挙げた版画は、同じ1600年、ハンガリーのパーパ城での、やはり同じくワロン兵による反乱の顛末です。失敗なのか見せしめなのかはわかりませんが、複数の反乱兵が通常(ふつうはまとめて絞首刑です)よりも残酷な方法で処刑されています。一方、反乱側の完全勝利に終わった「ホーホストラーテンの反乱(1602-1604)」は、当時の基準ではまずあり得ない条件の非常に稀有な事例です。
フランドル軍といえば「Munity」が代名詞になるほど、このような反乱はしょっちゅう起こっています。スペインが世界各国に展開している軍隊の維持費は天文学的で、国家破産も何度も宣言され、兵への給料の未払いも月単位ではなく年単位に及びます。フランドル方面軍の司令官は代々南ネーデルランド執政が務めていましたが、オーストリア大公アルプレヒトが初めて総司令官の地位を傭兵隊長であるスピノラ将軍に譲ったのは、彼に給与支払能力があったという点も大きかったのかもしれません。
小説の中のエピソードではありますが、『アラトリステ ブレダの太陽』でも、主人公たちフランドル兵は、比較的平和裏に話し合いで反乱を終わらせています。この物語の1625年時点では、さしものスピノラ将軍も、半年以上給与を払えないほどの貧窮に陥ってしまっています。
三十年戦争を経て、フランドル方面軍もオランダやスウェーデンの軍制改革を取り入れていきます。これら同様に兵士を将校に昇格させたりして将校の数を増やしましたが、逆に増やしすぎてしまい、将校1対兵士4という、非現実的な割合にまでなってしまいました。これが指揮系統の混乱や、さらなる給与未払いの悪循環の原因になったとも考えられています。
リファレンス
記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。
- Wilson, “Thirty Years War”
- クリステル・ヨルゲンセン他『戦闘技術の歴史<3>近世編』、創元社、2010年
- ジェフリ・パーカー 『長篠合戦の世界史―ヨーロッパ軍事革命の衝撃 1500-1800年』、同文館出版、1995年
- 『戦略戦術兵器事典<3>ヨーロッパ近代編』、 学習研究社、1995年
- マイケル・ハワード『ヨーロッパ史における戦争』、中公文庫、2010年
- ヴェルナー・ゾンバルト『戦争と資本主義』、講談社学術文庫、2010年
- リチャード・ブレジンスキー『グスタヴ・アドルフの歩兵/グスタヴ・アドルフの騎兵』、新紀元社、2001年
- ウェッジウッド『ドイツ三十年戦争』、刀水書房、2003年