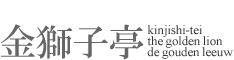Costumes of All Nations (1882)
この時代の、戦時における軍人の格好です。平時および一般の服装に関しては、「八十年戦争期の男性ファッション」へ。武器については「八十年戦争期の武器」を参照ください。
ここでもウィキメディアの肖像画を用いて、軍装の変遷を簡単に追ってみました。画像はすべて「ウィキメディア・コモンズ」のロイヤリティーフリー画像です。
自軍の識別色
Van der Maes (1617) 「オレンジの旗を持つハーグ市民軍の旗手」
16世紀-17世紀前半の軍隊には制服がなかったので、色で敵味方を判別しました。紋章学とも深いかかわりがあり、家ごと・国ごとに中世以来の伝統に則った色を用います。将校は肩帯や冑の羽飾りにこの色を用い、一般の兵士はリボンやストラップを服のどこか良く見えるところに結んだり縫い付けておきます。
オレンジ色は、オランダ軍を識別するカラーとして使われました。もちろん、オランイェ公(オレンジ公)が由来です。ウィレム沈黙公時代から反乱軍に、その後オランダ共和国が成立してからはオランダ軍に引き継がれました。
オランダは現代でも非常にわかりやすいかたちでこの伝統が残っており、サッカー等各種スポーツのオランダ代表はオレンジ色のユニフォームが多いです。オリンピックなど見ていると、ほとんどの競技でオレンジ色かと思います。
サッシュ(肩帯・飾り帯)
サッシュは14世紀頃から使われ始めたもので、幅広の布製のベルトです。冑を着けなくても所属がわかる、布一枚の手軽なものなので、制服が登場するまでの間は軍人にとって必須アイテムとなりました。とはいえ同じものを支給されたりするわけではなく、銘々が独自に好きなものを用います。鎧の上から着けますが、平時でもサッシュだけは平服の上から着けていることも多いです。
ナッサウ家の人物やオランダ軍の将校たちの肖像画も、大抵オレンジ色の肩帯をした状態で描かれています。ちなみに、スペインをはじめとしたハプスブルク家は赤です。スペイン軍将校の肖像画は赤い肩帯をしています。
Workshop of Jan Antonisz. van Ravesteyn (1609-1633)
無地だけでなく、柄物もあります。左は「ニーウポールトの戦い」の英雄のひとりナッサウ伯ローデウェイク=ヒュンテル。右は彼によって捕虜となったスペインのメンドーサ提督。それぞれオレンジと赤のベースに、金糸をふんだんに使ったレースと、多色使いの花模様の刺繍が施された、かなり派手な柄の肩帯を掛けています。
戦争の途中、スペイン側からオランダ側に寝返った傭兵などで、オレンジ色の肩帯の調達が間に合わなかった部隊の将校たちは、肩帯は赤のまま、通常右から左に掛けるところを逆の左から右にして戦ったそうです。なんだか乱戦になったら、お互いから敵に間違われてしまいそうですが。もっとも、肖像画には、左から右に掛けている状態で描いてあるものもいくらでもあるので、掛け方については実はあまり厳密な決まりはなかったのかもしれません。
Anthony van Dyck (circa 1634) / Gerard van Honthorst (1640)
また、肩から掛けるのではなく、腕や腰に巻いているものもよく見かけます。もともと「サッシュ」自体が腰に巻くものを指していたので、本来肩掛けのほうがイレギュラーともいえます。これは左腕にリボン結びしているカリニャーノ公トンマーゾ=フランチェスコと、マフラーのように首巻きしてるライン宮中伯モーリッツ。
Unknown (1622-23)
怪我をした場合は、三角巾代わりにも使えて便利? ブラウンシュヴァイク公クリスティアンは左手を切り落とすほどの怪我をしていて、それ以降の肖像はこのようにサッシュで腕を吊った状態で描かれています。
羽飾り
Michiel Jansz. van Mierevelt (1600-1641)
戦時においてサッシュおよびストラップは、連隊単位でほぼすべて同じ色をつけると考えて差し支えありませんが、冑につける羽飾りはその限りではありません。たとえば、オランダのナッサウ家の人間は肩帯・羽飾りともにオレンジですが、ドイツのナッサウ家の人間は肩帯がオレンジ・羽飾りがナッサウ家の色である青を使ったりもしました。1色に限られたわけでもなく、2-3色ミックスして使っている場合もあります。上記のオランイェ公フィリップス=ウィレムはハプスブルク側の人間ですが、羽飾りの色は家の色を用いたオレンジと白です。
サッシュよりも小さな単位(中隊ごとなど)での所属を表すことにも使っていたといえます。
この羽飾り、もちろん所属を表したり富を誇示したりするものではありますが、意外に実用的でもあり、混乱した戦場で司令官の位置を確認する目印にもなります。1590年イヴリーの戦いで、アンリ四世は、自分の白の羽飾りを目印にするよう部下に伝えています。(白は目印にするには探しづらい気もしますが…)。逆に司令官自身が部隊からはぐれてしまって、部下がその羽飾りを頼りに探し当ててくれたなんて逸話もあります。
甲冑
軍人に何より欠かせないのが身を守る鎧です。16世紀後半から17世紀前半にかけては、前世紀の数十kgにも及ぶ鋼鉄鎧から、制服の前段階であるバフ・コートに至るまでの、ちょうど過渡期にあたります。野戦砲などの火器の発達とも無関係ではありません。鋼の鎧を着ていて、仮にマスケット銃の弾ははじくことができたとしても、大砲の弾が直撃したら、鎧を着ていようが布の服を着ていようが、その致死率には大差ないともいえます。なおこの時代のヨーロッパでは、長弓も楯も実戦では既にほとんど使われません。
Complete Armor for Combat (16th century)
北イタリア製の鎧。オーストリア大公アルプレヒトがニーウポールトで着ていた鎧が「白銀の鎧」とされているので、こんなぴかぴかなタイプだったのでしょう。ミラノやニュルンベルク製の鎧が高級とされました。
「オーストリア大公アルプレヒトがニーウポールトで着ていた鎧」は、「古典的なスタイルの漆黒の鎧」と書かれてるものもありました。どうやら途中で着替えたらしいです。戦闘前に士気を鼓舞する際は目立つ銀の鎧、戦闘中は実用的で動きやすい(しかも敵の的にならない)黒の鎧と使い分けたようです。
Alonso Sánchez Coello (ca. 1570)
鎧の下には、金属の衝撃をやわらげるため、キルトの上衣(ダブレットなど)を着用しました。上のフェリペ二世は、チェインメイル(鎖かたびら)も着込んでいるようです。鎧自体の装飾も凝っていますね。
3/4鎧
Titian (1548)
あまりにも有名なティツィアーノのカール五世。鎧自体の丈は腿あたりから長くて膝くらいまでで、「四分の三 three-quarter」鎧と呼ばれるものです。全身鎧よりも機動性がよく、この16世紀後半-17世紀前半の主流になります。この絵ではまだ馬にも装飾が施されていますが、馬鎧や馬服はほとんど見られなくなっていきます。
Armor of Jacopo Soranzo (1560-1570)
騎士団章のついているめずらしいタイプ。というより、普段サッシュで隠れている部分なので、案外こういうタイプも見えないだけで多かったのかもしれません。色ツヤかたちは至ってスタンダードな3/4鎧です。
全身鎧
Anthony van Dyck (ca. 1620)
こちらはヴァン・ダイクのカール五世。脚部分を覆う脚鎧を含んだこれが全身鎧(complete)です。重騎兵などが突撃時の重さを出すために着用しました。(重騎兵突撃の威力たるや、戦車がぶつかってくるくらいの衝撃らしいです)。しかし着用者の負担も相当なもので、実際、『鉄腕ゲッツ行状記』などを読んでも、鎧を着て行軍している途中、暑さで息ができなくなって死んでしまう、というケースも何度か出てきます。
Golden armor of Herman Wrangel (17th century)
17世紀の全身鎧は肖像画用や儀礼用となっているものもあります。画像はスウェーデン元帥ヘルマン・ウランゲルの黄金鎧。金はやわらかいので、金色のものはほとんど鍍金です。こんな派手で目立つもの戦場で着てたの?と疑問に思えますが、「黄金鎧を着ていた」という記述も案外出てくるので、ちゃんと実用に耐えるものでもあったようです。
Armour of Alexander Farnese (1857: photo) / Details
パルマ公アレサンドロ・ファルネーゼの鎧一式。盾や馬具(いずれも儀礼用と思われます)まで派手柄で揃えてあります。さすが王族といったところ。下に置いてあるもうひとつの冑は、フルフェイスではない実戦用の替えでしょうか。
胸甲(キュイラス)
昔のRPGなんかで「むねあて」とされていたやつがコレです。3/4鎧から、腕部分(ものによってはさらに腰から下のスカート部分)を取ったもの。金属や皮革でできています。この胸甲だけは、鎧が廃れて制服になっていっても、弾除けの最後の砦として近現代まで残ったようです。
Wybrand de Geest (1630-1632)
ナッサウ伯エルンスト=カシミール。黒い部分だけが胸甲でスカート部分はバフ・コート(後述)です。よーく見ると胸甲は縫い目っぽいものが見えるので、金属製ではなく皮革製のようです。両手も金属製の手甲ではなく、ブーツと同じ色の皮手袋に変わっています。
冑
Spanish conqueror helmet (17th century)
最もポピュラーなものが、マスクのないシンプルな帽子タイプ。飾りのないプレーンなものは一般兵士にも支給され、中南米を征服したコンキスタドールもこんなのを被っています。将校や貴族の場合は、上のパルマ公の甲冑一式のように鎧本体と一対のデザインで、さらに頭頂部に羽飾りがつけられるようになっています。
Henri Ambrosius Pacx (1620-30s?) “Prince Maurice of Orange during the Battle of Nieuwpoort”
だんだんこの冑も帽子に取って代わられていくようになりますが、17世紀はじめくらいまでは、重騎兵は冑をかぶり続けていました。この「ニーウポールトの戦い」の絵では、中央のナッサウ伯マウリッツは帽子をかぶっていて、左下に描かれた従者が冑を持ち歩いています。右側の冑をかぶっている将校たちが騎兵、逆に左側の将校たちは皆帽子なので歩兵将校とわかります。
ちなみに、このマウリッツが着ている黄金鎧は、1612年頃に議会から全身肖像画作成用に贈られたもので、もちろん1600年のニーウポールトの戦い当日には存在していないものです。また、平時に黒の服しか着ていなかったのと同様、戦時に好んで着ていたのも、飾りの一切ない真っ黒な鎧だったようです。
Parade armour (16-17th century)
司令官クラスの貴族はこのようなフルマスクタイプのものを着用することもあります。鼻と口を覆うマスク部分は可動式で、顔だけ出して被ることも可能です。17世紀に入ると、実際に戦場で顔全体を覆うのはレアケースだったのではないかと思われます。オーストリア大公アルプレヒトは顔を隠していたおかげで(顔を出していたにも関わらず、という説もありますが)、配下の兵士から誤ってハルバードで殴られて怪我をしたことがあり、また、フランドル方面軍総司令官のスピノラ将軍は常に顔を覆った状態で着用していましたが、「今時めずらしい」として当時でも話題にのぼったほどです。この時代の肖像画でも、冑は被らずにサイドテーブルに置いて描いてあることが多いです。
Armour of Charles III, Duke of Lorraine (1580-1590)
こちらはロレーヌ公着用の、おそらくサヴォイア風鎧。サヴォイアの冑は目の部分の開きかたに特徴があります。マスク部分が上下可動式なのではなく、左右に開くようになっているのかと思われます。
English Civil War armour (17th century)
イングランド内戦の際に使用された冑。顔全体を覆うのではなく、鼻筋に沿って1-3本の棒だけがついているものです。「突く」は避けられませんが「斬る」の回避には有効です。『クロムウェル』の映画でも出てくる冑はほとんどこれです。なお、この画像の右下には、当時の将校・兵士の日当が書いてあったりします。
盾・楯
Adam van Breen (1611-1618)
上に、「楯はほとんど実戦では使われない」と書きましたが、教練書は存在しています。軽歩兵の丸型の楯(右)だけではなく、重歩兵のような巨大な楯(左)を用いての、それぞれ剣や槍の教練です。楯を亀の甲羅のように背負っている絵画もよく見かけます。マウリッツ公が自分の護衛隊に持たせていたようで、マウリッツとフランシス・ヴィアーはそれぞれ、護衛のこの丸楯のおかげで銃撃を免れたことがあるそうです。大楯はローママニアのマウリッツが若気の至りで作らせて護衛に持たせてみたようですが、重くて機動性が悪く(おそらく評判も悪く)、2-3年で使われなくなりました。
バフ・コート
革製の上衣。ヘラジカの革でつくられていて非常に高価なので、将校以上のレベルが用いました。1610年代から登場したようですが、1630年前後の絵画によく見られるようになります。時期柄、三十年戦争やイングランド内戦で活躍した元帥や将軍たちに、このコートを着ている肖像画が多いです。絵画ではかなり黄色味の強いベージュや黄土色で描かれていますが、実際の色はトープ色(ピンクがかったグレー)がいちばん近いようです。
Matthäus Merian (1632)
スウェーデン国王グスタフ二世アドルフ。赤の上着(ポーランドの「デリア」と呼ばれるコート)の下に着ている黄色い服がバフ・コートです。バフ・コート自体は革の特性上水を含むと重くなり乾きにくいため、悪天候のときなどは、このようにさらに外套を重ねることもありました。一般的には袖なしが多いようですが、グスタフのコートには袖付きのものもありました。
Gustav II Adolf’s Buff Coat (1627)
1627年のポーランドとの戦争で肩に怪我を負った国王グスタフ二世アドルフは、鎧の着られない体になってしまいました。(画像はディルシャウの戦いでグスタフの着ていたコート)。鎧の着れない国王を先頭に立てて戦場に赴くのも、ほかの将軍たちにとってもやりにくい…ということもあったかもしれません。当然、金属に比べれば強度は劣ります。アンリ四世時代のサーベルチャージは、冑までフル装備の重騎兵による攻撃でしたが、スウェーデンのサーベルチャージは、このバフ・コートを着た軽騎兵によるものです。いかに白兵戦での危険度が増したか想像がつきますし、国王自身も5年後のリュッツェンで戦死しています。
元帥杖
Unknown (ca.1650) Portrait of Johann Ludwig von Erlach
日本語では「元帥杖」と訳しますが、持つのは元帥に限りません。古くはエジプトからあり、軍事司令官がその指揮権の象徴として持つものです。杖(ステッキ)のイメージとは若干違って、長さは長くても50cm程度。英語でそのまま「バトン」といったほうが、カッコ良さは半減しますが、形状は伝わりやすいかもしれません。元帥杖にまでその所属を表す模様がつけられたのはおそらく17世紀中頃からで、それまでは何の変哲も無い茶色か黒の棒です。
このページも含め、鎧を着ている貴族の軍人の肖像では大抵の人物が元帥杖を持って描かれているので、この項目の画像にはあからさまにフランス百合紋の描かれたものを選びました。スイス出身のエルラッハ元帥は、テュレンヌ大元帥より一時代前のフランス元帥。傭兵あがりではありますが、グスタフ二世アドルフ、ザクセン=ヴァイマール公ベルンハルトなど錚々たる司令官のもとで軍事経験を重ねてきた人物です。元帥の称号を受けたわずか3日後に死去しているそうです。
A.デュマの『ダルタニャン物語 ブラジュロンヌ子爵』のラストシーンを知っている人であれば、このフランス元帥杖の画像と、エルラッハ元帥のエピソードにちょっとニヤリとするかもしれませんね。
兵士の服装
ここまでは貴族や将校の服装でした。兵士はもっと軽装です。とはいっても、バフ・コートの時代になると、あまり将校と見た目の違いはなくなってきます。
Jacob de Gheyn (1607)
1607年出版の『武器教練』から火縄銃兵のイラスト。派手で分かりやすい彩色のものを選びました。頭にはシンプルな冑、上衣も非常にシンプルなダブレットとガーメントの重ねです。手は素手で、腰に剣を挿しています。右腰には火薬入れを提げています。
Pikesmen in Marbury
歴史再現イベントの様子(ぜひ拡大図で見てください)。左奥のほうに車が見えるのはご愛嬌。パイク(長槍)兵たちは、頭には鉄製のヘルメットをかぶっていますが、手前の部隊は胸甲を着けている兵もいるものの、基本的にはシャツに皮革製キュイラスまたはダブレット程度の装備です。何人か混ざっている肩帯の人物は将校役でしょう。一般兵よりも高級そうなダブレットを着ていたり、羽根つき帽子をかぶっています。
Musketeers in Marbury
こちらはマスケット兵。何人かは制服みたいな上着を着せられていますが、頭はヘルメットではなく帽子です。斜めがけしているのは肩帯ではなく薬莢入れです。デ・ヘインの絵と似ていますね。
制服
Adam van Breen (1618)
制服も16世紀後半から部分的に取り入れられるようになります。貴族の近衛兵などが着ている揃いのお仕着せが制服のはしりのようです。(『もうひとりのシェイクスピア』でもオックスフォード伯の家人はすべて家紋入りの上着を着ていました)。
画像はオランイェ公となったばかりのマウリッツが1ダースほどの護衛たちに先導させている様子です。青のマントと矛槍で揃えたこの護衛兵は相続財産のひとつでもあり、父のオランイェ公ウィレムから引き継がれ、弟のフレデリク=ヘンドリクに継承されました。
Frans Pietersz. de Grebber (1618)
集団肖像画によくあるようなオランダ諸都市の市民軍(軍とは名ばかりのブルジョワクラブの場合も多々ありますが)も、衣服あるいは画像のようにサッシュを揃えたりしています。ドイツ領邦の民兵軍などでも、布地をまとめて仕入れる関係から、制服に準じるものがあったと推測されます。
Parrocel Joseph (1678)
参考まで。17世紀でよく見る制服といえば、『三銃士』の「フランス国王の銃士隊」。青地に十字のマントで、映画や本の挿絵などによく見られますが、実際の『三銃士』『二十年後』の時代(ルイ十三世麾下の1620年代から1640年代まで)の絵画に描かれているものは探せませんでした。ここに挙げた絵は1661年以降、ルイ十四世の時代になって再編成されてからのものです。逆に赤地に十字のマントのリシュリュー枢機卿の護衛隊は、1629年のマントヴァ継承戦争の頃を描いた絵画があります。
Nicolas Prévost (1640?)
いずれにしても最初の四半世紀は、やはり傭兵が主体なため、兵はほとんどばらばらの格好です。軍として揃いの制服がそれとわかって見られるようになるのは、イングランド内戦あたりからかと思われます。
リファレンス
記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。
- クリステル・ヨルゲンセン他『戦闘技術の歴史<3>近世編』、創元社、2010年
- ジェフリ・パーカー 『長篠合戦の世界史―ヨーロッパ軍事革命の衝撃 1500-1800年』、同文館出版、1995年
- 『戦略戦術兵器事典<3>ヨーロッパ近代編』、 学習研究社、1995年
- マイケル・ハワード『ヨーロッパ史における戦争』、中公文庫、2010年
- ヴェルナー・ゾンバルト『戦争と資本主義』、講談社学術文庫、2010年
- リチャード・ブレジンスキー『グスタヴ・アドルフの歩兵/グスタヴ・アドルフの騎兵』、新紀元社、2001年