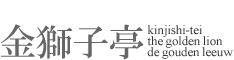Willem Hendrik Schmidt (19th century) ハンストするエミリア(歴史画) In Wikimedia Commons
八十年戦争期の貴族の倫理観は、建前と現実の差を見てもあってないようなものではあり、不貞行為は日常茶飯事です。が、そのような中でもやはり一線を越えたものは、人の口の端にのぼるようなスキャンダルとなります。ナッサウ家ではそんなスキャンダルが、ザクセン公女アンナとその娘・孫娘三代に渡って続きました。その度にオランイェ=ナッサウ家は恥をかかされることになり、当主たちはその火消しに追われることになります。
かといって、その当主たち全員にもそれぞれ庶子が居て、身持ちが良いわけでは決してありません。それでも彼女たちのスキャンダルが、当時の基準に照らしても特異なものだったことは確かです。
ザクセン公女アンナ
Unknown (16th century) In Wikimedia Commons
ザクセン選帝侯モーリッツの一人娘で、オランイェ公ウィレム一世の二番めの妻。人物記事はこちら→ ザクセン公女アンナ
ほとんどは個別の記事にも書きましたが、故郷のディレンブルクに逃亡中のウィレムが「反乱」のために奔走している間、アンナは田舎暮らしを嫌ってケルンで浪費生活をしていました。もともとブリュッセルの宮廷でもその奇行によってたびたびウィレムを困らせていたアンナでしたが、ケルンでは雇った弁護士ヤン・ルーベンスと不倫関係に陥って、1571年8月、不義の子まで産んでしまいます。自分の身に覚えのない子供の誕生、というこの上ない恥辱に、さすがにウィレムも我慢がならず、1571年12月、子供の認知を拒否して一方的にアンナとの離婚を申し出て、自分はさっさと次の結婚相手を探し始めました。
実際にこのスキャンダルの尻拭いをしたのはウィレムの次弟のヤン六世です。平民と貴族の奥方との不倫関係ともなれば、即刻命を取られてもおかしくない時代です。しかし、激情にまかせて処刑、というのもさらなる恥の上塗りとなると考えたヤン六世は、ヤン・ルーベンスの献身的な妻の取り成しもあって、彼の一命だけは助けます。ヤン・ルーベンスには死ぬまで監視がつくことになりますが、普通に生活を営むことも許され、そのしでかした事の重大さに対しては相当に寛容な措置が与えられたといって良いでしょう。この事件の後に生まれたのがのちの画家ピーテル=パウル・ルーベンスであり、ヤン六世は間接的に後世の美術史に寄与したことになります。
アンナの側は、実家のザクセンが離婚と彼女の受け入れを断ったため、しばらくヤン六世の所有する城のひとつに監禁されることになりました。この監禁生活の中、アンナはますます精神を病み、結果的に命を縮めることにもなります。ウィレムは1575年6月、シャルロット・ド・ブルボンと再婚しました。ここに至って観念したザクセンでは、しぶしぶながらアンナを引き取り、選帝侯の城内の窓の無い部屋に幽閉しました。アンナはそこで衰弱死しています。
オランイェ公女エミリア
Unknown (17th century) In Wikimedia Commons
オランイェ公ウィレムとアンナの間の次女で、ナッサウ伯マウリッツのすぐ下の全妹。人物記事はこちら→ オランイェ公女エミリア
幼少期はディレンブルクで過ごし、長じてからは姉たちと生活していたため、男性や結婚には全く興味がなかったようです。姉たちの死亡や結婚でひとりになってしまうと、兄マウリッツを頼ってハーグにやってきて、その宮廷をとりしきる女官長の役につきました。1597年、そんな兄が軍事遠征で留守中、ハーグへ亡命してきたポルトガル公マヌエルと、エミリアは電撃的な恋に陥ります。
三十路近くまでまったく恋愛経験のなかったエミリアの行動はエキセントリックでした。すぐに戦地の兄のもとに単身押し掛けて、マヌエルとの結婚の許可を求めます。ちょうどこのとき、義母のルイーズ・ド・コリニーがフランスへ出かけており、他の姉妹たちも既に全員結婚等で片付いていてハーグに居らず、女性の相談相手がなかったということもこの行動の一因かもしれません。しかしマヌエルは庶子のうえカトリック教徒であり、客観的に見ても、到底マウリッツが許すはずがありませんでした。
頭に血ののぼったエミリアはハーグに帰るや否や、11月7日、勝手にカトリックの司祭に秘密結婚の式を挙げさせてしまいます。11月末、ハーグへ凱旋したマウリッツはそれを知って激怒し、マヌエルはヴェーゼルまで逃亡を強いられ、エミリアはマウリッツによって監禁されてしまいました。「やはりお前はあの女の血だ」とマウリッツに吐き捨てられ、エミリアはこのとき初めて母アンナの不行状を知った、とする説もあります。
しかしさらにエミリアの行動はエスカレートしました。離婚を強制しようとするマウリッツに対し、幽閉中一切の食べ物を拒否しました(冒頭の絵画)。つまり、「公女が餓死」という前代未聞の醜聞をタテにした、命懸けの脅迫です。そして翌12月には脱走してマヌエルを追って行きました。マウリッツはこの2人の追放を命じ、10年以上関係を絶ちます。1610年、父ウィレムの遺産分割の場で、義母ルイーズ・ド・コリニーや従兄ウィレム=ローデウェイクの執り成しによる和解の席が設けられますが、マウリッツはその表面上の和解後も決してエミリアに気を許すことはありませんでした。
ポルトガル公女マリア=ベルギカ
ポルトガル公マヌエルとエミリアの長女。厳密にいえば彼女はナッサウ家の一員ではありませんが、三代めとして当然その恥はナッサウ家にも降りかかりました。
マウリッツの死の翌年の1626年、ポルトガル公の一家はオランイェ公フレデリク=ヘンドリクの勘気に触れ、再度共和国からの追放を命じられました。カルヴァン派の母エミリアは娘たちを連れジュネーヴへと亡命します。
そんな1629年、マリア=ベルギカにバーデン辺境伯との縁談が舞い込みます。(人物の特定はされていませんが、この時期のバーデン家の適齢の男子は数も限られているため、消去法でいくと、相手はバーデン=デュルラハ辺境伯ゲオルク=フリードリヒの三男クリストフかと考えています)。この一家の境遇を思えば、この上ない良縁でした。しかし、バーデン辺境伯に仕える将校と恋仲になったマリア=ベルギカは、あろうことか結婚前夜にその将校ジャン=テオドール・クロールと駆け落ちしてしまいました。部下と婚約者に逃げられた辺境伯の面目は丸つぶれです。
ところでこの縁談と逃避行が何月のことか具体的にはわかりませんが、母エミリアが同年の3月16日に亡くなっているので、その前であれば死期を早めてしまった原因になってしまったかもしれません。逆にその後であれば、母が亡くなったからこその駆け落ちかもしれません。なお、ジャン=テオドールとの結婚の記録は6月なので、縁談から破談までのすべての出来事は半年以内に起こっています。ちなみに、このジャン=テオドールは絵に描いたような無責任男で、たった数年でマリア=ベルギカと別れるとあちこち放浪して歩いては、最終的に1643年、ヴェネツィアで殺されてしまいました。
マリア=ベルギカの妹たちは母の死後オランダへ帰国しましたが、マリア=ベルギカは生まれた子供たちを妹たちに預け、自分は単身ジュネーヴに残り、余生を一人で過ごしたようです。長女の起こした不祥事は、5人の妹たちのうち4人までを、生涯結婚から遠ざけてしまいました。唯一結婚した五妹マウリティア=エレオノーラの結婚はフレデリク=ヘンドリクの死の直後であり、ハーグの宮廷では、フレデリク=ヘンドリクによってポルトガル公女たちの縁談がきつく禁じられていた可能性も高いです。
Gerard van Honthorst (1636) In Wikimedia Commons 4妹のマウリティア=エレオノーラ(青)と末妹のサビーナ=デルフィカ(赤)
リファレンス
- Dr. Oma: The Healing Wisdom of Countess Juliana Von Stolberg
- Motlay, “United Netherlands”
- Kikkert, “Maurits”