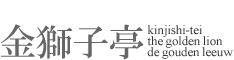コンデ公夫妻 (モンモランシーの聖マルティヌス聖堂参事会教会のステンドグラス)F. Ehrmann (19th Century) In Wikimedia Commons
三十年戦争の前哨戦ともいえる「ユーリヒ=クレーフェ継承戦争」には、国際戦争ならではのエピソードが随所に散りばめられています。メイン記事には載せきれない(むしろ筋を追うのには邪魔?)のでここに時系列でまとめました。逆にあらすじを知らないと何のことかよくわからないかもしれませんので、まずは下記をどうぞ。
メイン記事はこちら → ユーリヒ=クレーフェ継承戦争
何より、前半早いうちに暗殺されてしまうアンリ四世の存在感は大きいです。というか、この記事もほぼアンリ四世一色です。とくに、2番めのエピソードを書くために記事を分けたと言ってもいいかも…。
あの子がそなたを愛するようになったら、バソンピエールよ、私はそなたを憎まずにはいられまい。もしあの子が私を愛したら、そなたは私を憎むに違いない。不和は望まぬ。互いの友情を大事にしたい。
フランス国王アンリ四世/ ハインリヒ・マン『アンリ四世の完成』
アンリ四世の壮大な計画
アンリ四世とシュリー公の像 In Wikimedia Commons
アンリ四世は、この紛争を「千載一遇の好機」と捉えていました。国王の最大且つ最終目標は、ハプスブルク家の力を削ぐのみならず、同家を事実上世襲となっている皇帝位から引きずり降ろすことです。アンリ四世はユーリヒ=クレーフェの新領主と親密な同盟を結ぶことを公言し、当初はプファルツ=ノイブルク公を推していましたが、次代の皇帝家候補としてよりふさわしいと考え直し、途中からブランデンブルク選帝侯支援に鞍替えしました。
さらに、南ではサヴォイア公に対して子女の婚姻をエサにイタリア(スペイン領ミラノやジェノヴァ)の奪取を唆し、北ではオランダをけしかけてスペインとの休戦を反故にさせ、オランダはマース川沿い一帯、フランスはルクセンブルクへ版図を広げ、そのついでに「スペイン街道」を完全に分断できる、という図も描いていたようです。打倒ハプスブルクの「ついで」にしてはかなりスケールの大きな話でもありますし、フランスの利益のために他国の安全保障をも脅かしかねないムシの良い話でもあります。そもそもユーリヒ=クレーフェ継承の問題自体、帝国内で処理するべき話であり、本来フランス国王の干渉するところではありません。
しかし何より戦士を自称するアンリ四世は、自らスピノラ侯と戦い(しかも勝って捕虜にし)たがっていて、そのためオランダ軍のナッサウ伯マウリッツとの共同戦線を激しく希望していました。これらのプランが完遂できたと仮定して、シュリー公の試算したフランスの利益は国王の考えていた数倍におよび、それも国王の動機を強めることになったようです。
しかし『アンリ四世―自由を求めた王』を読むと、シュリー公が回想録に記した計画はさらに遠大なもので、現代のEU並の規模を持ったプランです。ユーリヒ=クレーフェ問題はその前座に過ぎない位置づけとなります。もっとも、それをシュリー公と国王とが完全に共有していたか、というところでは、回想録が書かれたのも王の死後かなり後のことなので確かなことはいえず、この本の著者も紹介に留める程度にしています。
アンリ四世の「老いらくの恋」
♪侯爵そなたは運がよい
あんな美人を妻にして
そなたのまことを示したくば
今彼女をば余にゆずれ『アンジェリク(2)』 画/木原敏江、解説/篠原秀夫 pp.309,352.
コミック『アンジェリク』の後半に何度も出てくる、アンリ四世を歌った民謡。2巻巻末の解説によれば、この民謡自体は王の愛人ガブリエル・デストレのことを歌ったものとのことですが、ユーリヒ=クレーフェ継承問題とほぼ同時に、またもやこんなアンリ四世の色恋沙汰が持ち上がりました。
Unknown (17th Century) バッソンピエール元帥 In Wikimedia Commons
王妃マリー・ド・メディシス主催のバレエのリハーサルを覗いていたアンリ四世は、15歳のシャルロット=マルグリット・ド・モンモランシーに一目惚れします。彼女にはバッソンピエール侯という婚約者が居ましたが、アンリ四世は彼女を自分の愛人とするため、バッソンピエール侯との婚約を解消させ、自分の親戚(従兄弟の子)ブルボン=コンデ公アンリ二世と結婚させることにしました。
独身の愛人に王妃の座を要求された過去のあるアンリ四世は、いったん誰かの妻にしてしまってから愛人にするという手続(?)を踏もうと考えていました。王子ルイが生まれる以前にアンリ四世が王位を譲ろうと考えていたほど、コンデ公は国王に近しい相手でもあり、男色家との噂もあったことから、シャルロット=マルグリットの仮の夫とするのに最適とされたようです。
Peter Paul Rubens (1610) シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシー In Wikimedia Commons
しかしこの時点でアンリ四世は55歳。40歳も年の差のある国王に言い寄られることをシャルロット=マルグリットは頑なに拒否しました。コンデ公もこの馬鹿らしい役回りに腹が立たないわけがなく、シャルロット=マルグリットが心の底から国王の求愛を嫌悪していることを知ると、妻にコロッと参ってしまいます。そしてある日、狩の最中に夫妻は揃ってこっそりと抜け出すと、フランス国境を越え、隣のスペイン領南ネーデルランドへ逃亡しました。
最初、コンデ公は南ネーデルランドは通過するのみの予定で、オランダのブレダを目指していました。オランイェ公フィリップス=ウィレムの妻がコンデ公の唯一のきょうだいである姉のエレオノールであり、その伝手でオランダへの亡命を求めました。が、共和国の法律顧問オルデンバルネフェルトは現在の国際状況を鑑みて即座に入国を拒否、夫妻はそのまま南ネーデルランド執政府のあるブリュッセルに逗留することになりました。
Gillis van Tilborch (1658) ブリュッセルのナッサウ伯の館 In Wikimedia Commons ブレダから駆けつけたオランイェ公夫妻の館に、シャルロット=マルグリットは一時期身を寄せました。
言うまでもなくアンリ四世は激怒します。「ヘレネを奪還する」とトロイア戦争に擬えて、即刻コンデ公夫妻を引き渡すよう、そうでなければ戦争も辞さないと執政のアルプレヒト大公に圧力をかけました。コンデ公側も必死なので、教皇、スペイン国王、聖界選帝侯たちに手当たり次第助けを求めます。しかしアルプレヒト大公としても、この面倒な時期にわざわざ面倒があちらからやって来て、はっきり言って迷惑以外の何者でもありません。言い分としてはコンデ公のほうが当然ながら正しいので、はいどうぞとフランスに返してやるわけにもいきません。
アンリ四世がユーリヒ=クレーフェ問題に対してフランス軍を出撃させると表明したのが1610年4月末。愛人を取り戻すため宣戦布告した、と揶揄されることもありますが、あくまでこの出兵は占領されたユーリヒに向けたものであって、ブリュッセルの大公に向けたものではありません。むしろ、いつドイツに向けて出陣するか、というタイミングを計っていたところにコンデ公問題が持ち上がり、渡りに船として利用した可能性もあります。いずれにしてもその直後の5月14日、アンリ四世は暗殺されてしまい、この問題も予期せぬ終わりかたをすることになります。
ちょっと調子に乗って、スペインの後ろ盾を得て「本来のフランスの次期国王は自分である」と表明していたコンデ公は、アンリ四世の暗殺後すぐにフランスに戻りますが、既に王妃マリー・ド・メディシスが摂政としてルイ十三世を即位させていた後でした。さらにその後、王妃マリーとの確執でコンデ公夫妻は投獄の憂き目にも遭います。なお、彼らの長男がのちに「大コンデ」と呼ばれるルイ二世です。
ラ・シャトル公の騎士道
Bernardus Mourik (1772) 「ユーリヒ攻囲戦 (1610)」 In Wikimedia Commons
この挿絵は、ユーリヒ撤退時に、敗戦側のラウシェンブルク連隊長がオランダ・フランス連合軍の将軍たちに下馬して挨拶したときの様子です。このときそれに応えて手を差し出したのは、老将ラ・シャトル公のみだったとか。ブランデンブルク選帝侯、プファルツ=ノイブルク公の両者は、「お帰りはあちら」とばかりににべも無い態度でしたが、もとはといえば皇帝側の無法な占拠のせいで攻囲戦を余儀なくされたわけですから、それも無理からぬことでもあるでしょう。
改宗の当たり年? 1613年
Circle of Hans von Aachen (after 1612) In Wikimedia Commons マティアスは戴冠式に出席したヤン八世に、侍従にならないか直接打診しています。
1613年7月、ユーリヒ=クレーフェ継承問題の当事者の一方、プファルツ=ノイブルク伯ヴォルフガング=ヴィルヘルムがカトリックに改宗(正式な改宗は翌年5月)し、11月には友人でもあるバイエルン公マクシミリアン一世の妹マグダレーネと結婚しました。さらにその直後の1613年12月にカトリック改宗を表明したといえば、ナッサウ=ジーゲン伯ヤン八世も挙げられます。
1610年のユーリヒ攻囲戦には、ヤン八世も兄のハンス=エルンストと共にオランダ側で参戦していました。オランダ軍での大規模攻囲戦としては初陣だったようです。というのもヤン八世は若年期のキャリアが兄弟たちとは若干違っていて、皇帝軍に加わりハンガリーで戦ったこともありました。教皇にも個人的な恩義があり、もともとカトリック側の有力者たちと独自の人脈を持っていたといえます。
そのためヤン八世の場合は既に1608年頃から密かにカトリック信仰を持っていて、表明する機会を窺っていただけなので、プファルツ=ノイブルク公の改宗や結婚に追随したというわけではなさそうです。しかし敢えてこの時期にカミングアウトした理由として、新皇帝マティアスの影響があったことは共通しているかもしれません。
ジェームズ一世の勝手な?計画
Simon Frisius (1613) In Wikimedia Commons ハーグにおけるナッサウ伯マウリッツへのガーター勲章授与式
第一次・第二次ユーリヒ=クレーフェ継承戦争のいずれでも、その舞台となったユーリヒの街。ナッサウ伯マウリッツが英国大使からきいたところによれば、ジェームズ一世は飛び地であるユーリヒを中立の第三者の手に委ねるつもりがあったようです。その候補者として、ヘッセン方伯、アンハルト侯、そしてマウリッツの兄のオランイェ公フィリップス=ウィレムの3人が挙げられています。
彼ら候補者が英国王からこの件を打診されていたのか、またマウリッツはこのことを単に事実として挙げているだけで、どういう意図で従兄のナッサウ伯ウィレム=ローデウェイクに伝えたのかはわかりません。しかし、この継承戦争に直接関係のないイングランドでさえ、このように思惑をもって介入していたことだけはわかります。
ジェームズ一世は、1610-1612年、穏健派牧師アルミニウス没後のレイデン大学の後任問題でもオランダ国内の宗教問題に介入しており、1613年には、まるでその際の助力へのお礼とでも言わんばかりに、ナッサウ伯マウリッツにガーター勲章を授与しています。また、王女エリザベスとプファルツ選帝侯フリードリヒ五世との結婚もこの時期で、かつてアンリ四世が考えていたように、ドイツひいては大陸での発言力の強化を目論んでいたのかもしれません。
リファレンス
記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。
- 栗原福也「十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国 二 ネーデルラント連邦共和国」『岩波講座 世界歴史(旧版)<15>近代2』、岩波書店、1969年
- クリステル・ヨルゲンセン他『戦闘技術の歴史<3>近世編』、創元社、2010年
- ジェフリ・パーカー 『長篠合戦の世界史―ヨーロッパ軍事革命の衝撃 1500-1800年』、同文館出版、1995年>
- Wilson, “Thirty Years War”
- Motley, “Life and Death”
- Prinsterer, “Archives”