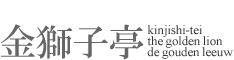デルフト新教会のオランイェ家墓所入口に置かれた花 In Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
「八十年戦争期の宗教」という概説記事を書いたため、こちらも対として。管理人は特定の信教を持ちませんが、個人の信教について推測を含んで言及する記事となるため、あらかじめご承知おきください。
「アウクスブルクの和議」(1555)から「ウェストファリア条約(1648)までの約1世紀の間は宗教戦争の世紀でもありました。その時代に生きた市民や領民たちは、自らの属する地の統治者の信教に翻弄されました。領主が改宗してしまえば、昨日までの自分たちの信教も迫害の対象になってしまうからです。が、その統治者自身は、領民たちと違って上からの強制力が(ほとんど)ないからこそ、自らの改宗については良心・政治と図ったうえで悩みぬいて行うことが大半であったと推測されます。
改宗は、自らの生活様式を一変させ、育ってきた環境や教育を否定することにもつながります。また、自分一人ではなく領地全体での問題、さらには近隣諸侯との関係性の問題ともなります。「決して改宗しない」という決心同様、「改宗する」との決断も相当な覚悟を要したはずです。
オランイェ公ウィレム一世
ジュネーヴ「宗教改革者の壁」のオランイェ公ウィレム In Wikimedia Commons
改宗: ルター派 → カトリック → カルヴァン派
カルヴァン派の中心地ともいえるジュネーヴで、20世紀初めに建設された「宗教改革者の壁」のモチーフには、コリニー提督やクロムウェルと並んでウィレムも選ばれています。しかしウィレムは決して、先頭に立って「宗教改革」をおこなった人物ではありません。
ウィレム一世については日本語でも訳本や論文が出ていますので、比較的その考えには触れやすくなっています。時系列でいうと、もともとルター派の両親に育てられたウィレムは、11歳のときにオランイェ公を継承すると同時に、神聖ローマ皇帝カール五世の宮廷に出仕します。この時にカトリックに改宗させられました。それ以降、「反乱」の初期までウィレムは旧教のままでした。周りの状況からやむなくカルヴァン派に改宗したのは、アルバ公の失脚とだいたい同時期の1573年10月になってのことです。
ウィレムの改宗は、フランス国王アンリ四世同様、多分に政治的なもので教義にとらわれることはありませんでした。彼自身の家族、母ユリアナや弟ヤン、そして妻シャルロットでさえも、彼の宗教観についてはあいまいで寛容すぎるとして不満を持っていたとのことです。もっとも彼自身は、表面的な作法としてのカルヴァン派信仰は保持し続けています。それでも、あまりにカルヴァン派による専横が過ぎる場合には躊躇を示し、また、反乱諸州の主権者候補としてフランス王室(1572年サン・バルテルミーの虐殺を指導したヴァロア朝)のアンジュー公を擁立したりと、他のカルヴァン派為政者層より一歩引いていたことは確かです。ウィレムの宗教観も「寛容」と表現されますが、これはのちの三男フレデリク=ヘンドリクとも非常に近く、どちらかといえば積極的な「寛容」ではなく、優先順位として宗教が他の要素よりもあまり重要視されていない、という印象を受けます。
ドイツ=ナッサウ家家長たち
フーメン改革派教会外壁のレリーフ In Wikimedia Commons
改宗: ルター派 → カルヴァン派
ウィレム一世の弟たちは、彼より1年早い1572年にルター派から改革派に改宗します。そのうち1574年に戦死したルートヴィヒとハインリヒを描いたレリーフがこの画像です。ただ一人残った弟で、ドイツナッサウ家の家督を継いだ次弟ヤン六世の信仰はどんどん厳格になっていきました。ヤン六世は兄ウィレム一世の信仰心が足りないとして不満を持っていましたが、逆に兄のウィレムはヤン六世が数年で過激になってしまったことにかなりのショック(ドン引きといっていいレベルで)を受けています。ヤン六世は自分の跡継ぎについても、「カトリックに改宗した者は継承権を失う」という決まりを制定しました。このヤン六世の影響を最も強く受けたのが、父とともにローティーンの頃に改宗したと思われる、長男のウィレム=ローデウェイクと次男ヤン七世です。
ウィレム=ローデウェイクはフリースラントの州総督となって以降、自分の周囲に文化人を多く配していましたが、もともとカルヴァン派の影響の強いレーワルデンで神学者たちに囲まれていたこともあり、自身が聖職者と遜色ないほどに神学について深い知識と興味を持っていました。何よりカルヴァン派内での「穏健派」と「厳格派」の派閥論争の際に、従弟マウリッツの最後の選択に重要な役割を担った人物でもあります。ドイツに住む父ヤン六世・弟ヤン七世とも頻繁に連絡を取り合っていますが、書簡の中でも普通に神学について論じてあるものがいくつもあります。親兄弟と日常的に信教についての意見を交わし合っていたことがわかります。
ヤン七世の場合は、兄のウィレム=ローデウェイクがオランダでの役割を優先させたことから、実質上の跡取りとなって父のヤン六世と生活を共にし、その宗教的な生活様式も完全に受け継いでいました。ヤン六世が居ながらにして書簡でプロテスタント・ドイツ内のネットワークを維持したのに対し、ヤン七世は自らプロテスタント・ヨーロッパのあちこちに赴き、顔をつなぐことでそのパイプをさらに強固なものにしています。家庭内でのカルヴァン派信仰の教育は非常に厳しいものでしたが、周囲とはルター派・カルヴァン派を問わず対等に付き合っています。
疑問なのが、これほどまでにプロテスタント・ドイツの要の位置にいながら、ナッサウ家は「ウニオーン(プロテスタント同盟)」にはまったく絡んでいません。まだその回答は探せていませんが、非常に興味深い課題のひとつです。
ナッサウ伯マウリッツ
van der Veken? (1618-1620) シント・アガタ修道院から国立博物館へ移設されたステンドグラス In Wikimedia Commons
改宗: 無し
叔父のナッサウ伯ヤン六世に育てられたマウリッツは、一貫して改革派教徒としての生活を送りました。たとえ戦場といえど毎日の礼拝を欠かさず、その日課は正確なものでした。父の死後その地位を受け継いだ時点では、周りの有力者たちもほとんどがカルヴァン派で占められていたため、父親が苦心したようなカトリックとの政治的な調整にはほぼ無縁だったと言えます。かといって個人的にもカルヴァン派以外の者を排斥する傾向はなく、有能でさえあればカトリックであろうがユダヤ人であろうが、信教を問わず取り立てています。
マウリッツの宗教面に関しては、十二年休戦期のカルヴァン派内部での抗争に巻き込まれてしまった際の行動にまつわるテーマが大きいです(「宗教論争からクーデターへ」参照)。本人は正直、「穏健派」と「厳格派」のカルヴァン派同士の内輪揉めなどにはまったく関心はなく、当初は「予定説が青だろうと緑だろうとどっちだっていいじゃないか」と語っていたほどです。むしろそういった意味では、「穏健派」に近い考えを持っていました。最終的にクーデター騒ぎやオルデンバルネフェルトの処刑、という強硬手段を採らざるを得なくなったのは、逆にそのように最後まで態度の留保を続けていたことが裏目に出た結果であるともいえるでしょう。
ここに挙げたステンドグラスは、自身の領地であるクエイク付近にある聖アガタ修道院に寄進したステンドグラスです。ステンドグラスの描くモチーフについては特に指定しなかったため、寄進を受けた修道院の側がマウリッツを描いたようです。製作年代は、クーデターにほぼ決着がついた1618-1620年と推測されています。礼拝時の姿ではありますが、着ているものは鎧なので、宗教人というよりも軍人としての描写の色が強いと思われます。
ナッサウ=ジーゲン伯ヤン八世
ジーゲンのUnteres Schlossのプラーク In Wikimedia Commons)
改宗: カルヴァン派 → カトリック
詳細はヤン八世の人物記事に譲りますが、八十年戦争期のナッサウ家の中ではおそらく唯一の「敵」方の人物です。それも最初からではなく、ヤン八世も一族の他の男子と同じように教育を受け、少なくとも成人するまではカルヴァン派貴族としてのアイデンティティに特段の疑問もなかったはずです。たまたま他の兄弟たちと違って、軍人としてのキャリア形成の場がオランダではなく、比較的カトリックの影響を受けやすい地域やサークルだったことに加え、本人がカトリックの信仰に傾倒していったのが1608年頃からとのことですから、弟アドルフの死も契機になっている可能性があります。
いずれにしてもヤン八世に関しては、本人が改宗のカミングアウトの際に書いたものが複数残されているので(管理人は未読)、その内容を精査すれば信仰を替えるに至った動機はうかがい知ることができるはずです。1つは日記?小論文?の形式のもので、改宗に至る経緯を自らの内面に問いかけながら書き留めたもの、もう1つは父ヤン七世に対する書簡です。書簡のほうがやや簡潔に書かれており、その手紙に対するヤン七世の返書のほうが長いくらいです。
その後、伯父のウィレム=ローデウェイク(上記のように厳格なカルヴァン派)が弟のヤン七世に宛てて、ヤン八世を思いとどまらせるのはもう無理だ、という諦めのような短い書簡を送っています。これを見るに、実の父はともかく、オランダ側ではある程度の理解は得られたと考えられ、ヤン八世自身も改宗したからといって、即何かしらのペナルティは受けていません。
1617年、長兄のハンス=エルンストが病死し第一相続人となると、実家に押しかけて領地の継承権を主張します。そして激怒した父ヤン七世から、「カトリックに改宗した者は継承権を失う」との規定に署名を強制されます。それでも、その後いったんオランダに戻り、マウリッツのクーデターの手伝いをしながら父親にその顛末の手紙を送ったりしているので、ここに至っても家族との間に大きな亀裂のある様子は見えません。
むしろサヴォイアへの派兵を契機に南ネーデルランド執政府の策に取り込まれ、カトリック貴族と縁組をしたことが、一族との決定的な決裂の始まりになりました。その後は皇帝軍・スペイン軍に在籍してオランダ軍またはその友軍と戦い、父の死後、領地の継承についても武力行使でナッサウ=ジーゲン領を乗っ取るかたちになりました。『アウクスブルクの和議』による信仰属地主義から、カルヴァン派の一大中心地のひとつであったナッサウ=ジーゲン領はカトリックが強制されることになります。
その他ヤン八世についての参考記事
「ナッサウ伯領の軍制改革」
「グラディスカ戦争」
オランイェ公フレデリク=ヘンドリク
Bosschaert (1650) 海の支配者としてのフレデリク=ヘンドリクの寓意画 In Wikimedia Commons
改宗: なし
オランイェ公フレデリク=ヘンドリクの宗教観についてはほとんど知られていません。(兄マウリッツから「決して人前で宗教について語るな」と言われたのを忠実に守ったからかどうかはわかりませんが)。フレデリク=ヘンドリクについてはその州総督在任時代がオランダの「黄金時代」とかぶることから、本人が何かしら表明したというよりは受け身的に「寛容」とされている印象を受けます。
フレデリク=ヘンドリクは、母親が熱心なユグノーのコリニー家の出身なので、当然信徒としてはカルヴァン派です。また、宮廷牧師アイテンボハールトの教えを受けてきたために「穏健派」に近いと言われています。が、アイテンボハールトのミサには兄のマウリッツも毎日出ていましたし、「厳格派」の従兄ナッサウ伯ウィレム=ローデウェイクの影響も決して少なくはないはずなので、彼自身の信条をすべてアイテンボハールトに帰してしまうのはやや乱暴な議論な気もします。
マウリッツの死後、亡命していた穏健派牧師たちが続々帰国したのも、フレデリク=ヘンドリクが進んで帰国を促したり許可したからというよりは、単に黙認の様相が強いです。アイテンボハールトも帰国していますが、再び彼の宮廷牧師となることはありませんでした。また、政治犯であるグロティウスに関しては決して帰国を許可しなかったという側面もあります。軍事的には、ファン・デン=ベルフ伯の造反受け入れやリシュリュー枢機卿との同盟など、外部カトリック勢力との共闘にも積極的です(「南ネーデルランド分割構想」参照)。
オランダの黄金時代は絵画でも有名ですが、ここに挙げたような寓意画も多く描かれています。ローマ風の衣装にギリシア神話の神々、さらにカトリックのモチーフなどが折衷でなんでも有りです。ウェストファリア条約直後には、このように少なくとも絵画には、既に特定の宗教観は感じられなくなっています。
ナッサウ=ハダマール伯ヨハン=ルートヴィヒ
after van Hulle (1717) 1648年のウェストファリア条約を記念した版画 In Wikimedia Commons
改宗: カルヴァン派 → カトリック
ヤン六世の息子でありながら、遅くに生まれているため、兄ヤン七世の息子(彼にとっては甥)たちよりも年下です。彼も宗教的な成長過程は兄弟や甥たちとまったく同じくカルヴァン派の教えに基づいたものでしたが、軍人には向いていなかったのか、あるいはちょうど成人になる頃に休戦が重なったからか、若年期から外交を任されるようになりました。
三十年戦争が始まると、プファルツから北ドイツにかけてが戦場となり、その通り道に当たるナッサウ領は両軍から多大な被害を受け続けました。ヨハン=ルートヴィヒはその折衝能力からもともと皇帝との交渉を何度かおこなった経験がありましたが、1629年、ナッサウ家家族会議の末、最も弁が立つという理由でウィーンの皇帝の宮廷に送られます。皇帝フェルディナント二世はヨハン=ルートヴィヒの能力を高く買っていたものの、戦争の激化に伴い年々プロテスタント貴族を遠ざける傾向を強めていたため、ヨハン=ルートヴィヒはイエズス会士ラモルマイーニの助言を受けてカトリックへの改宗を決意します。これも家族会議の総意として、採るべき策のひとつとしてあらかじめ合意していたものでした。
この版画にあるように、やがてヨハン=ルートヴィヒは皇帝の紋章を戴き、皇帝の代理として外交を担っていくことになりますが、その最低限の条件としてカトリックの保持は必要な条件だったでしょう。皇帝がフェルディナント三世に代替わりすると、急進的過ぎるイエズス会士が皇帝の周りから遠ざけられ、ヨハン=ルートヴィヒはその能力のみをもってさらに重用されるようになります。
なおヨハン=ルートヴィヒも、ヤン八世と同じく『アウクスブルクの和議』の信仰属地主義により領地の再カトリック化をしなければなりませんでした。が、その方法や進捗は非常に緩やかで、妻がカルヴァン派に留まることや子女へのカルヴァン派教育も認めていました。ヤン八世は荒廃したオットー系ナッサウ伯領をすべて自分のものとしカトリック化しようという野心を持っていました。非常に逆説的ですが、領地の教化に消極的なヨハン=ルートヴィヒや裏技を使ったゾフィー=ヘートヴィヒがカトリックに改宗したことで、結果的に彼の野心に楔を打ち込んだかたちになります。
このようにヨハン=ルートヴィヒの改宗は、家を守るという目的のための全体善を考えたもので、結果として家を真っ二つにしてしまったヤン八世のアプローチとは相当にベクトルが違っていたものといえます。
ブラウンシュヴァイク公女ゾフィー=ヘートヴィヒ
Rudolf Fuchs (20th century) ゾフィー=ヘートヴィヒのフレスコ画 In Wikimedia Commons
改宗: ルター派 → カルヴァン派 → カトリック → (カルヴァン派)?
ナッサウ=ディーツ伯エルンスト=カシミールの妻。もとはルター派として育ったと思われますが、結婚と同時にカルヴァン派に改宗し敬虔なカルヴァン派信徒として知られました。彼女が力を発揮するのは夫の死後です。長男は成人していたもののオランダでの地位と役割を期待されていたため、ゾフィー=ヘートヴィヒがいったん寡婦領としてナッサウ=ディーツを相続し、結果としては長男が戦死して次男に領地を相続させるまでの8年間、後見人の立場でディーツを治めました。
その目的は義弟ナッサウ=ハダマール伯ヨハン=ルートヴィヒとまったく同じです。オランダ、とくにレーワルデンの宮廷で各国の貴族との交流を結んでいたゾフィー=ヘートヴィヒも、女性ながらヨハン=ルートヴィヒに劣らず交渉能力に恵まれていました。ナッサウ伯領の軍隊通行の禁止を求めて、ゾフィー=ヘートヴィヒは皇帝や近隣の諸侯に宛てて相当数の手紙を書いています。その過程で、ウィーン宮廷で地位を得つつあったヨハン=ルートヴィヒの勧めに従い、ゾフィー=ヘートヴィヒもカトリックに改宗しました。しかしこれは実はある意味の裏技で、「女性である自分は単なる後見であり為政者ではない(=信仰属地主義の対象外である)」との論理で、ナッサウ=ディーツ領はあくまで被後見人の長男ヘンドリク一世カシミールの信教(カルヴァン派)に属するべきと主張しました。つまり自分ひとり改宗するに留めて、領地全体の信教を保ったといえます。
ゾフィー=ヘートヴィヒは後見を降りてからその死までの2年間、オランダに戻りアルンヘムに在住しましたが、そこでまたカルヴァン派に戻ったかどうかははっきりしません。死後はレーワルデンのナッサウ家墓所であるカルヴァン派の大教会に埋葬されています。
リファレンス
- 通史・研究ガイド カテゴリ内の書籍
- ウェッジウッド, C.V. (瀬原義生 訳)『オラニエ公ウィレム―オランダ独立の父』文理閣、2008年
- “ADB”
- “NDB”